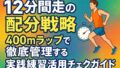400m通過の早見表やチェックリストを用意し、「やること」と「やらないこと」を明確化して失速要因を削ります。下の要点リストを手元に置き、8〜12週の計画へ落とし込んでください。
- 目標はVDOT/臨界速度から逆算し、現状テストで妥当性を確認する
- 週2ポイント(LT系・VO2系)+つなぎの質で“走力総量”を作る
- フォーム/ドリル/登坂でエコノミーを底上げし無駄な力を削る
- ピーキング期は量を落としつつ速さの刺激を途切れさせない
- 400m通過と許容ブレ幅を事前に決め、当日は淡々と刻む
目標設定とペース基準の作り方
最初に決めるべきは「どの15分台を狙うか」です。15:59と15:10では必要な代謝特性も練習配分も異なります。ここではVDOTや臨界速度(CV)といった客観指標から、1000m当たりの目標ペースを逆算し、400m通過へ落とし込みます。加えて1500m/3000mテストの結果から換算して、無理のないゾーンを見極めます。
15分台の定義と必要生理指標
15分台はVO2max・LT・エコノミーの三本柱。VO2maxは上限、LTは持久の支え、エコノミーは同一速度での酸素消費低減です。LTペースはだいたい1時間レースの平均速度、CVは約30〜40分レベルでの持続速度目安です。
VDOT・臨界速度からの目標ペース算出
最近の練習やレースからVDOT/CVを推定し、1000mペースを決めます。例えば15:30目標なら3:06/km前後、CVは約3:10/km付近が一般的な基準になります。
現状把握テストと換算(1500m/3000m)
週のどこかで1500mまたは3000mの全力テストを実施し、換算表で5000m見込みを更新。3000mの×1.7〜1.75は簡易目安です。
目標別ペース早見表と通過管理
400mごとの通過設定を先に決めると、当日の配分が安定します。誤差は±1秒/400m以内を基本とし、風や集団の状況で微修正します。
練習配分の原則と疲労コントロール
おおまかな配分は有酸素ボリューム70%・LT20%・VO2/速さ10%が目安。疲労は可逆ですが、慢性化させないラインを守ります。
| 目標タイム | 1000mペース | 400m通過 |
|---|---|---|
| 15:00 | 3:00/km | 72秒 |
| 15:10 | 3:02/km | 73秒 |
| 15:20 | 3:04/km | 73〜74秒 |
| 15:30 | 3:06/km | 74秒 |
| 15:45 | 3:09/km | 75秒 |
| 15:59 | 3:12/km | 76〜77秒 |
- 1500m/3000mの最新結果を用意する
- VDOT/CVを推定し1000mペースを決める
- 400m通過と許容ブレ幅(±1秒)を設定
- 週2ポイントの質・量を逆算して配置
- 2週ごとに換算値を更新し微調整する
- テストは疲労が抜けた状態で実施
- 向かい風の区間は集団走で省エネ
- カーブは短内側で距離ロスを抑える
- GPSの誤差よりトラックの通過時計を信頼
- 練習は目的別ペースを守る
LT・VO2maxを伸ばすキー練習
15分台では、LTの底上げとVO2maxの刺激が両輪です。LT走で「少しきつい」を長く保つ能力を作り、1000m系インターバルで酸素摂取の上限を引き上げます。つなぎの強度を間違えると疲労が抜けず、逆にポイントの質が落ちます。ここでは再現性の高い設計を示します。
閾値走の設計(連続/分割)
連続20〜30分のLT走は基礎。分割(例: 10分×2/レスト2分)なら心拍を高く保ちつつ負担を管理できます。
1000m系インターバルの最適化
代表例は1000m×5〜6(R=200m jog)。目標が15:30なら1本3:02〜3:06で揃え、ビルドアップは不要、等速を徹底します。
クルーズインターバルの活用
LT付近の1600m×3〜4(R=60〜90秒)は持久の柱。呼吸は荒いが制御可能な域を維持します。
| メニュー | 目的 | ペース目安 |
|---|---|---|
| LT走20〜30分 | 閾値向上 | 10km想定ペース |
| 1000m×6 | VO2刺激 | 5000m想定-0〜+3秒/1000m |
| 1600m×4 | LT強化 | 10km-5〜10秒/km |
| 2000m×3 | CV刺激 | CV付近 |
| テンポ走15分 | 持久維持 | マラソン〜ハーフ間 |
- 週の前半にLT、後半にVO2を配置
- レストは短すぎず長すぎず(1000mなら60〜90秒)
- 最後の1本だけ上げず等速で揃える
- つなぎjogは会話可能な強度
- 翌日のボリュームは削らず強度のみ下げる
- 呼吸と接地のリズムを一定に保つ
- ピッチはやや高めで接地時間を短縮
- 暑熱時はペースより心拍/主観で管理
- 路面/風の影響を考え周回/トラックを選ぶ
- トレーニングログは必ず数値と感覚を併記
スピード持久とランニングエコノミー
同じVO2maxでも、エコノミーが良い選手は楽に速く走れます。ドリルやレペでフォームを整え、登坂で筋腱を強くして接地の剛性を高めましょう。ここでの目的は「速さそのもの」より、速さを維持するコストを下げることです。
レペティションとストライド
300〜600mのレペはフォームを崩さずにスピード域を触る練習。R=完全回復で質を担保します。
ドリルとフォーム矯正
スキップ、バウンディング、A/Bドリルで骨盤前傾と接地位置を整える。腕振りは後方へ引く意識で推進力を得ます。
登坂走と筋力/腱の強化
4〜6%の坂で12〜20秒ダッシュ×8〜10。地面反力の使い方を覚え、平地に戻しても伸びを実感できます。
| 内容 | 時間/本数 | 狙い |
|---|---|---|
| 300mレペ | 6〜10本 | フォーム維持 |
| ストライド | 80〜120m×6 | 可動域/接地 |
| 登坂ダッシュ | 12〜20秒×8 | 筋腱剛性 |
| ドリルA/B | 10分 | ピッチ/荷重 |
| 流し | 100m×4 | 刺激維持 |
- ポイント翌日は短いストライドでほぐす
- ドリルは毎回5〜10分入れる
- 登坂は週1まで、やり過ぎない
- 動画で自分のフォームを確認する
- シューズは用途別に使い分ける
- 腰高を保ち骨盤を前へ運ぶ
- 接地は体の真下を意識
- 呼吸は2拍吸って2拍吐くリズム
- 腕振りは肘角一定で後方へ
- 視線は15〜20m先で安定
週間メニュー設計と期分け
8〜12週の中期計画で、週2ポイント+αを核に進めます。最初の4週でLTの土台、次の4週でVO2刺激を強め、最後の2週でピーキング。ボリュームは波を作り、回復週を挟んで上げすぎを防ぎます。
8〜12週の全体像とボリューム
週走行距離は体力に応じて調整し、ポイントの質を落とさない範囲で増やします。目安は50〜90km/週。
ピーキング2週の絞り込み
テーパリングは量を20〜40%落とし、速い刺激は維持。流しや短レペで神経系を保ちます。
疲労指標と調整日の入れ方
主観的疲労、安静時心拍、睡眠、脚の張りを記録。指標が悪化したら即座に調整日を入れます。
| 週 | 走行距離 | ポイント例 |
|---|---|---|
| 1 | 60km | LT20分/1000m×5 |
| 2 | 65km | 1600m×4/坂ダッシュ |
| 3 | 50km | 回復週+ドリル多め |
| 4 | 70km | 2000m×3/レペ400m×6 |
| 5 | 75km | LT30分/1000m×6 |
| 6 | 55km | 回復週+流し |
- 週の序盤にLT、終盤にVO2を置く
- 回復週を3〜4週に1度入れる
- ロングjogは会話可能な強度で
- ドリル/流しで毎回フォーム確認
- 睡眠と栄養の赤字を作らない
- ポイント翌日はジョグ+流しで軽く
- 疲労が抜けない時は本数を削る
- 暑熱時は時間管理へ切替
- シューズのローテーションを固定
- 週末はコース条件に近い環境で実施
レース戦略と当日運び
当日は400mの通過管理が命。スタートの混雑とアドレナリンで最初の400mが速くなりがちですが、+2〜3秒までの余裕を許容し、その後に定速へ戻します。風・集団・コーナーでの微差が累積し、ラスト1000mの余力を左右します。
400mごとの通過目安と配分
目標に応じて72〜76秒のレンジで管理。ラップブレは±1秒以内に抑えます。
風・集団走・コーナリング対策
向かい風は隊列の3〜5番手に位置取り。コーナーは最短距離で走り、膨らみを避けます。
ラスト1000mの意思決定
残り1200mで肩と呼吸を確認し、残り800mから段階的に加速。最後の直線で上体を前に運び切ります。
| ラップ | 通過秒目安 | 配分メモ |
|---|---|---|
| 400m | +0〜+2 | 突っ込み防止 |
| 800m | ±0 | 定速へ収束 |
| 1600m | ±1 | 隊列で省エネ |
| 3000m | ±1 | 呼吸と腕振り再確認 |
| 4000m | −1〜0 | 軽く押す |
| 残り1000m | −1 | 段階ビルド |
- スタート直後は接触回避を優先
- 風向きに応じて位置取りを調整
- 周回は最短ラインを死守
- 毎周回で腕振りと接地を点検
- 残り800mから肩を下げて前傾を維持
- 時計は通過地点のみで見る
- ラップのズレを焦って帳尻合わせしない
- 給水は少量で喉湿らす程度
- シューズは軽量/反発のバランス型を選択
- 寒暖差に応じてアップ時間を調整
補給・体調管理・怪我予防
速く走るには、練習×栄養×ケアの三位一体が不可欠です。鉄不足や体重管理、睡眠の赤字はすべてパフォーマンス低下につながります。レース前の補給は軽く、消化に良い炭水化物中心で、直前の水分は取りすぎに注意。痛みの芽は早期に摘みます。
レース前〜直前の補給戦略
前日は糖質中心に補給し、当日は2〜3時間前に軽食、30〜45分前にジェル少量が目安。
体重/鉄/ビタミンDとコンディション
体重は急に落とさず、月0.5〜1.0kgの緩やかな変化で。鉄・ビタミンDは血液検査で不足を確認します。
足底/膝/ハムのケアと強化
足底・膝周り・ハムは傷みやすい部位。エクセンントリック系の補強と可動域の確保が鍵です。
| 項目 | タイミング | ポイント |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 前日〜当日 | 低脂肪・低食物繊維 |
| 水分/電解質 | 当日朝〜直前 | 少量を分割 |
| 鉄/ビタミンD | 日常 | 不足は医師相談 |
| 補強(腱/足底) | 週2〜3 | 痛みゼロ域で |
| 睡眠 | 常時 | 7〜9時間 |
- 前日は消化に良い主食を中心にする
- 当日朝は固形を食べ過ぎない
- アップ後は冷えないよう保温
- 痛みが出たら練習の質を落として様子を見る
- 月1回はフォーム動画を撮って確認
- ジェルは銘柄を事前に試す
- シューズの寿命を管理する
- ストレッチは反動を使わない
- 冷却/温熱を使い分ける
- 練習ログに睡眠/体重も併記する
まとめ
5000mで15分台を安定して出すには、科学的な目標設定、週内の緻密な配置、そして当日の配分が必要です。VDOT/CVから目標ペースを決め、400m通過を事前に固定。週2ポイント(LT/VO2)とドリル/登坂でエコノミーを磨き、ピーキング期は量を落として速さの刺激だけを残します。補給・体調・怪我予防はすべて結果に直結します。
ここまでの表とチェックリストをそのまま運用すれば、失速の確率は大きく下がり、再現性のある自己ベスト更新に近づきます。今日の練習から、等速と目的ペースの厳守を合言葉に進めていきましょう。