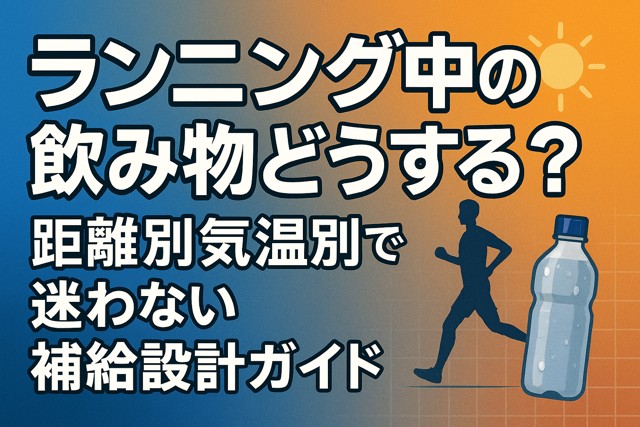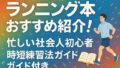- 目安は「ml/kg/時」。体重×目安値であなたの時間当たり必要量が概算できます。
- 迷ったらスポーツドリンクを基本に。長時間や猛暑は電解質比率をやや高める。
- 発汗テストで個人差を反映。ボトル重量の変化で発汗量を推定できます。
- 距離別に「どこで」「どれを」飲むかをテンプレ化し、当日迷わない仕組みに。
- 低ナトリウム血症や胃トラブル回避のため、薄めすぎ/一気飲みを避け小分け補給。
シーン別の基本戦略(ジョグ・ポイント練・レース)
まずは日々の練習シーンでの考え方を整理します。
強度や所要時間、気象条件、コース環境(自販機や給水所の有無)によって、飲む量も中身も変わります。
ここではジョグ、ポイント練習(インターバルやビルドアップ、閾値走)、ロング走、そしてレース本番でのタイムライン管理までを通貫で提示します。どの場面でも共通する原則は「のどが渇く前に少量を分割」し、「電解質のベースを確保」することです。
ゆっくりジョグの飲み方
低強度のジョグでも、30〜60分を超えるとパフォーマンスと気分に差が出ます。涼しい日で60分以内ならラン前後で合計500〜700mlを目安にし、走行中は口を湿らす程度の50〜100mlを10〜15分おきで十分。暑熱下や日差しが強い日はスポーツドリンクを基本にし、ミネラルを取り逃さないようにします。甘さが苦手なら水+タブレットで電解質を補うと胃が軽く保てます。
インターバルやビルドアップ時の補給
高強度では吸収が追いつかず、胃が揺さぶられるため、休憩の合間に一口ずつ取るのが鉄則です。アップ前に200〜300ml、セット間に各50〜100ml、クールダウン後に300ml程度を基準に。糖濃度が高すぎると腸に水が引き込まれて腹部不快が起きやすいので、スポドリは規定濃度〜やや薄めが安全です。カフェインは心拍を押し上げるため、夜のポイント練では用量に注意します。
ロング走とペース走での給水設計
90分を超えるロングでは、炭水化物と電解質の同時設計が不可欠です。基本はスポドリを主役にし、30〜40分ごとにジェルやバナナなどの固形を組み合わせます。胃が重いと感じたら一時的に水へ切替え、電解質はタブレットで補填。休憩を入れる場合は「止まって一気に飲む」よりも「歩きながら小分け」が失速を防ぎます。
レース当日のスタート前とスタート後
スタート60〜90分前に300〜500ml、30分前に100〜200mlを目安にして、直前のがぶ飲みは避けます。スタート直後は混雑で取りにくいので、最初の給水所で焦らず確実に摂る行動計画を。紙コップは上部をつぶして飲むとこぼれにくく、喉に入れる量も調整しやすくなります。
季節差と汗量の考え方
同じ強度でも夏と冬では発汗量が大きく異なります。夏は塩分ロスが大きく、冬は乾燥による体感差とトイレ問題が課題です。季節に合わせて濃度・量・頻度のいずれかを変え、発汗テストの結果を基準に自分のレンジを把握しましょう。
| シーン | 量の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| ジョグ(〜60分) | 50〜100ml/15分 | 電解質を薄く確保 |
| ポイント練 | セット間に各50〜100ml | 濃すぎ厳禁 |
| ロング走 | 200〜250ml/20〜30分 | ジェル併用 |
| レース前 | 300〜500ml(60〜90分前) | 直前は少量 |
| 暑熱時 | 個人発汗量に応じ増量 | 塩分を上げる |
- のどが渇く前に少量を分割して飲む。
- 電解質のベースを常に確保する。
- 濃すぎる甘味は避け、胃の負担を減らす。
- セット間や給水所で落ち着いて摂る。
- 季節と発汗量で量を微調整する。
- タブレットや粉末で濃度を都度調整できる準備。
- 紙コップは上をつぶして飲むとこぼれにくい。
- ボトルの温度管理で飲みやすさを維持。
- 甘さに敏感なら水+塩タブの構成に。
- カフェインは時間帯と量を管理。
分割補給と電解質の維持、そして濃すぎ回避が、全シーンでの共通キーワードです。
気温・湿度・発汗量で変わる目安(ml/kg/h)
同じ人でも、気温や湿度が変わると必要量は大幅に変動します。万人に当てはまる絶対値は存在せず、推奨値はあくまでスタート地点。ここでは発汗テストで個人基準を作り、気象に応じて「ml/kg/時」を上下させる方法を紹介します。湿度が高いと汗は蒸発しにくく、体表のベタつきの割に体温が下がらないため、補給頻度の微増が有効です。
発汗テストのやり方
トイレを済ませたらウェア込みで体重を測定し、ボトルの重量も計量。1時間走り、摂取した水分量と終了後の体重を記録します。発汗量(ml/h)=体重減少(g)+摂取量(ml)−尿量(ml)。これを体重で割れば「ml/kg/h」の個人係数になります。複数条件で実施して、暑熱・温和・寒冷の3レンジを持つと運用が楽になります。
気温・湿度別の摂取目安
温和(10〜18℃)ではおよそ5〜8ml/kg/h、暑熱(25℃超・湿度高)では8〜12ml/kg/h、寒冷では3〜5ml/kg/hが目安です。ただし個人差が大きいので、係数に±20%の可変域を持たせ、のどの渇きと尿の色(淡いレモン色が目標)で微調整します。
低ナトリウム血症を避ける塩分設計
水だけを大量に飲むと血中ナトリウムが薄まり、頭痛・吐き気・意識障害などのリスクが高まります。長時間や猛暑では、ナトリウムを含むスポドリやタブレットを活用し、1時間あたりの塩分目安を確保しましょう。発汗量が多い人ほど重要です。
| 条件 | 量の目安(ml/kg/h) | 補足 |
|---|---|---|
| 寒冷 | 3〜5 | 頻度はやや低めでOK |
| 温和 | 5〜8 | 標準的なレンジ |
| 暑熱 | 8〜12 | 塩分と頻度を増やす |
| 高湿度 | +1〜2 | 蒸発しにくく体温上昇 |
| 高高度 | +1 | 乾燥で喉が渇きやすい |
- 発汗テストで自分の係数を把握する。
- 気温・湿度で係数を上下に微調整する。
- 尿の色と量で過不足を確認する。
- 長時間は塩分を必ず組み込む。
- 前日からの水分・睡眠も整える。
- 同じコース・同じ装備で複数回テストする。
- 秤は0.1kg単位より0.05kg刻みが望ましい。
- 汗拭きで体重が増減しないよう注意。
- カフェイン摂取時は利尿に留意。
- 塩タブは汗の味(しょっぱさ)でも調整。
個人係数の可視化と気象条件の補正が、量の迷いを消します。
飲み物の種類と使い分け(水・スポドリ・経口補水液・カフェイン)
ランニングで使う飲み物は、大きく水・スポーツドリンク・経口補水液(ORS)・カフェイン系ドリンクに分けられます。どれが「正解」ではなく、強度・時間・気象・胃腸の相性でベストが変わります。ここでは各飲料の長所短所を整理し、場面に応じたブレンドや濃度調整の考え方を提示します。
水とミネラルの基礎
水は最も軽く安価で、口当たりが良く胃に優しいのが強み。長所は「どこでも手に入る」こと。短所は塩分がないため、長時間では電解質不足に傾くことです。ミネラルタブレットを併用すれば、軽さと安全性を両立できます。
スポーツドリンクと電解質の最適化
糖とナトリウム、カリウムを含み、吸収速度の面でラン向き。高強度や長時間では基本選択肢となります。甘さが苦手なら規定量よりやや薄めに作り、吸収と胃の快適さのバランスを取ります。冷やし過ぎは腹部への刺激になるので、常温〜やや冷たい程度が無難です。
経口補水液・カフェイン・ジェル併用の判断
ORSは脱水時の補正力に優れますが、平常時に多用すると味が濃く感じられる人も。レース中の緊急是正や暑熱適応初期に限定的に使うと機能します。カフェインは集中力と自覚的疲労低減に効く一方、利尿と心拍上昇を招きます。ジェルは30〜40分間隔で小分けし、水または薄めのスポドリで追うと吸収が安定します。
| 種類 | 向く場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 水 | 短時間・低強度 | 長時間は電解質不足 |
| スポドリ | 中〜高強度・長時間 | 濃度と温度に注意 |
| 経口補水液 | 脱水兆候・猛暑 | 常用は味負担大 |
| カフェイン系 | レース後半の集中 | 時間帯と用量管理 |
| ジェル | 30〜40分間隔 | 水で追って吸収安定 |
- 基本はスポドリ、水は電解質で補強。
- 暑熱や不調時のみORSをポイント投入。
- ジェルは小分け+水追いで胃を守る。
- カフェインは開始時刻と睡眠を考慮。
- 味に飽きたら氷やレモンで変化を。
- 薄め方は味覚だけでなく汗量で調整。
- 常温〜やや冷たい温度帯が無難。
- 粉末タイプは携行性が高い。
- ボトルに目盛りを付け消費量を可視化。
- 緊急用に塩飴を1〜2個常備。
基本=スポドリ、補正=ORS、味変=水+タブという考え方で迷いを減らしましょう。
距離別の給水設計(5km・10km・ハーフ・フル)
距離が変われば戦略も変わります。5kmとフルでは、喉の渇き・吸収速度・ロスタイムの許容が全く異なります。ここでは距離別に「スタート前」「レース中」「最終盤」の設計をテンプレ化し、当日のオペレーションをシンプルにします。
5km・10kmでの最小ロス戦略
5kmはスタート前の仕込みが9割。60〜90分前に300〜400ml、30分前に100〜150ml、直前は口を湿らす程度。レース中は給水所をスキップしてもOKですが、暑熱時は1回だけでも確実に。10kmは1〜2回の短時間給水で十分です。
ハーフマラソンの計画と失速回避
ハーフは給水の精度差がタイムに直結。スタート前の仕込みはフルとほぼ同じにし、5kmごとに200ml前後を目安に。後半のカフェインは利尿と相談し、ジェルは10〜12kmで1本、18km付近でもう1本を検討します。
フルマラソンの分割戦略と補給所活用
フルは「少量・高頻度・確実」が全て。5kmごとに200ml前後で、暑熱時は中間点で追加。前半から塩分を薄く入れ、30km以降は味覚の変化を見て水とスポドリを使い分けます。コップ取りは手前側は混むので中央〜奥を狙い、口をすぼめて一気に飲まず小口で。
| 距離 | 基本方針 | 注意点 |
|---|---|---|
| 5km | 事前仕込み重視 | 暑熱時のみ給水 |
| 10km | 1〜2回短時間補給 | 混雑回避 |
| ハーフ | 5km毎200ml | 後半のジェル |
| フル | 少量高頻度 | 塩分を前半から |
| 暑熱全距離 | 頻度と塩分増 | 胃負担を監視 |
- スタート前の仕込みを距離に合わせる。
- 給水所の位置を事前に把握。
- 少量を確実に摂る練習をしておく。
- ジェルは水で追って吸収を助ける。
- 後半は味に飽きる前に切り替える。
- 紙コップは中央〜奥のテーブルを狙う。
- 手でコップ口をつぶすと飲みやすい。
- 混雑時は一歩外側に出て安全確保。
- 喉だけでなく舌と口蓋を潤す意識。
- 吐き気が出たら水に切り替えて落ち着かせる。
距離別テンプレで判断を自動化し、ロスの最小化と失速回避を両立しましょう。
時間帯とコンディション別の飲み方(朝・夜・起床直後・食後)
同じ距離でも、朝と夜で体の状態は大きく違います。睡眠時間・前回食事・仕事による疲労・アルコールの影響など、コンディションごとに飲み方を変えると安全で快適に走れます。ここでは代表的な状況別のポイントを整理します。
朝ラン前後の水分と糖質バランス
起床直後は軽い脱水状態。走る30分前に300ml前後の水または薄めのスポドリを摂り、バナナや小さめのエナジーバーで糖質を少量。終了後は体重の1〜1.5%を目安に補水し、朝食でタンパク質と炭水化物をバランス良く補いましょう。
夜ラン・仕事後の注意点
日中のカフェインやストレスで交感神経優位になっている場合、心拍が上がりやすい傾向。開始前にゆっくり200〜300ml、走行中は少量分割、終了後は就寝までの利尿を考えて量を管理。アルコールは脱水を助長するため、走る日は控えるのが賢明です。
トレーニング後の回復ドリンク設計
終了後30分は回復のゴールデンタイム。スポドリまたはココアミルクなど吸収の良いドリンクで糖と水分を戻し、塩分も忘れずに。固形の食事が取りにくい場合はプロテインシェイクも有効ですが、濃すぎは胃に重いので量を調整します。
| 状況 | 基本ドリンク | 補足 |
|---|---|---|
| 起床直後 | 水または薄めのスポドリ | 300ml前後 |
| 朝ラン後 | スポドリ | 体重の1〜1.5% |
| 夜ラン前 | 水 | 200〜300ml |
| 夜ラン後 | 水+軽食 | 就寝まで利尿に注意 |
| 高疲労時 | ORS | 短期是正に限定 |
- 起床直後はまず軽く補水する。
- 夜はカフェインとアルコールの影響に注意。
- 終了後30分の回復を逃さない。
- 就寝予定時刻から逆算して量を決める。
- 胃腸の状態に応じて濃度を調整する。
- 朝は温かい飲み物で胃腸を起こすのも有効。
- 夜はミネラルウォーターで味の刺激を減らす。
- プロテインは水で薄めて小分けに。
- 回復食に塩気を少し足すと吸収が安定。
- 就寝直前の一気飲みは避ける。
時間帯の生理に合わせた補水で、睡眠とパフォーマンスを同時に守りましょう。
携行・補給所・現実解(ボトル・自販機・コンビニ)
理想的な計画も、現場に合わせた運用ができなければ絵に描いた餅です。携行ツールの選び方、補給所の取り方、自販機やコンビニの使いどころを押さえ、都市でも山でも「飲みたい時に確実に飲める」状態を作りましょう。
携行ツールの選び方と揺れ対策
短時間ならハンドフラスク、長時間やトレイルならベスト型やウエストボトルが便利です。揺れは擦れやフォーム崩れの原因になるため、身体に近い位置で固定し、ボトルの空気を抜いて液面の動揺を減らします。ストロー付きソフトフラスクは小口で飲みやすく、分割補給と相性が良いです。
補給所の取り方とロスタイム削減
距離看板や地図で位置を把握し、手前から減速・進路変更。テーブルは中央〜奥を選び、1杯を確実に。口をすぼめて小口で飲み、余ったら首筋に軽くかけて体温を下げます。ジェルを飲む直前に水を一口含むと、のどに残りにくくなります。
自販機・コンビニの活用と緊急時プロトコル
都市ランでは自販機やコンビニをピン留めしておくと安心。猛暑日は日陰側のルートを選び、店舗前で立ち止まって落ち着いて補給します。緊急時(めまい・吐き気・鳥肌)には走行を中止し、ORSや塩分を優先して体温を下げましょう。
| 手段 | 利点 | 注意点 |
|---|---|---|
| ハンドフラスク | 素早い一口 | 片手占有 |
| ウエスト型 | 重量分散 | 揺れやすい |
| ベスト型 | 容量と安定 | 夏は蒸れ |
| 自販機 | 入手容易 | 小銭・キャッシュレス |
| コンビニ | 多品目 | 寄り道のロス |
- ルート上の補給ポイントを事前にマーク。
- 携行は用途と時間で選ぶ。
- 飲む姿勢を練習してこぼしを減らす。
- ジェルの前後は水で口を湿らす。
- 異変時は無理せず即中断する。
- ボトルは半分以下になる前に補充。
- 暑い日は白や銀のボトルで温度上昇を抑える。
- キャッシュレス決済を腕ポーチに。
- 小さめの氷袋を首元に当てると楽。
- 帰路に補給ポイントを多く配置する。
道具選択と事前マップで、現場の不確実性を小さくしましょう。
まとめ
ランニングの飲み物戦略は「個人の発汗係数×気象補正×距離別テンプレ」という三本柱でシンプルに運用できます。まず発汗テストであなたの「ml/kg/h」を把握し、気温・湿度に応じて幅を持たせる。レースやロング走ではスポーツドリンクを基本に、味や胃の状態で水・ORS・ジェルを切り替え、小口・高頻度で確実に摂る。
朝夜や疲労度、コース環境に応じて量と濃度を微調整し、携行ツールや補給所の取り方を事前に練習しておけば、脱水・低ナトリウム・胃トラブルを避けつつタイムも体調も両立できます。最後にもう一度、のどが渇く前に少量を分割、電解質のベースを確保、濃すぎを避ける――この3点を習慣化すれば、あなたの走りはもっと安定し、暑い日も寒い日も「走り切れる自分」に近づけます。