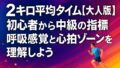- 直線主体で起伏は小さいが橋・IC部で小刻みなアップダウン
- 海風の影響が大きく復路は向かい風になりやすい
- 折返しは江の島入口付近と西湘二宮IC付近の2か所
- マイボトル前提のエコ給水で手元補給が重要
- 複数関門あり配分ミスはDNFに直結する
コース全体像と特徴(高低差と景観と難所)
湘南の海岸線を東西に伸びるコースは、視界が広く一定リズムを刻みやすい一方で、単調さによる体感ペースの乱れと海風の抵抗がパフォーマンスを左右します。スタートは大磯西IC付近の広い直線で、整列時点からの動線管理が肝心。前半は江の島入口付近で折返して再び西へ、後半は西湘二宮IC付近で2回目の折返しを行い大磯プリンスホテルへ戻ります。高低差は概ね15m程度の範囲に収まり、橋梁・インターのランプに伴う短いアップダウンが脚に微妙な刺激を与えます。視界に富士山や江の島が入り、気分が上がる反面、序盤にオーバーランしやすいため、意識的に抑える知性が必要です。
スタートとフィニッシュの動線
スタート直後は幅員が広いものの、ウェーブやブロックの前後で合流が起き、体感以上にブレーキが多発します。フィニッシュは会場内へ段階的に絞られます。ゴール手前は観客が増え、加速したくなりますが、舗装の継ぎ目・微上りに注意してフォームを崩さないことが大切です。
折り返しポイントと直線区間
江の島入口の折返しは応援が濃くテンションが上がる地点。Uターン後の流れに乗りすぎると以降の西行き向かい風で失速しやすいので、直後500mは呼吸を立て直します。西湘二宮IC付近の折返しは脚が重くなる30km以降に位置し、心理的な切り替え点として機能します。
高低差と橋・インター付近の起伏
コースは基本フラットですが、橋梁・ランプ部の短い上り下りでストライドが乱れがちです。ピッチで刻む意識に切り替える、登りは接地時間をやや延ばし腰高を維持、下りはブレーキをかけず股関節から畳むなど、フォームの微修正を準備しましょう。
風と潮の向きの傾向
冬季の北〜北西風が卓越しやすく、海沿いは遮蔽物が少ないため復路で向かい風を受けがちです。単独走になると出力が嵩み失速要因となるので、同等ペースの小集団を活用しドラフティングで省エネを図ります。
景観と応援が増える地点
江の島周辺や茅ヶ崎・辻堂の海浜公園前などは沿道が賑わい、メンタルを押し上げるポイントです。応援区間はピッチを2〜3/分上げる等、リズム調整でポジティブな揺さぶりを活かします。
| 区間 | 距離目安 | 要点 |
|---|---|---|
| スタート〜辻堂 | 0〜15km | 巡航確立と渋滞回避を両立 |
| 江の島入口折返し | 15〜21km | テンション上げすぎ注意 |
| 中盤西行き | 21〜32km | 向かい風に備え省エネ走法 |
| 西湘二宮IC折返し | 32〜37km | 脚作りとメンタル再起動 |
| 大磯フィニッシュ | 37〜42.195km | フォーム維持で押し切り |
- 序盤は設定より5〜10秒/km抑えて酸素負債を回避
- 橋・ランプはピッチ優先で上下動を抑制
- 海風は集団を活用し出力の無駄を削減
- 折返し直後は500mだけ再整流を意識
- 景観の高揚に対し呼吸数でペース制御
- 視認性の高いラップ表示で客観管理
- 腰高維持と骨盤前傾を意識
- 接地の真下化でブレーキ回避
- 肩甲帯の脱力で風抵抗最小化
- ストライドは後半まで温存
注意:海風と単調さでオーバーペースになりやすい区間構成です。序盤の数秒抑制が後半の数十秒短縮に化けます。
前半0〜21kmの区間攻略
前半は巡航ペースの「型」を作るフェーズです。スタート直後は合流で速度変動が起きるため、心拍・主観的運動強度(RPE)で管理し、スピードメーター的な時計表示に振り回されないこと。江の島入口の折返しまでは視界が開け、体感スピードが上がりやすいので「抑えているのに速い」を合言葉に巡航へ移行します。
スタート〜5kmの渋滞回避
広い直線でも合流点でボトルネックが発生します。ジグザグ追い抜きは距離ロスと筋疲労を招くため、前後の間隔に余裕を持ち、ライン取りは緩やかなアウトインで最小限に留めます。
5〜15kmの巡航ペース確立
追い風気味なら少ない出力でキロ数秒の貯金を作れますが、貯金の作りすぎは禁物。呼吸2拍吸気2拍呼気など、テンポで安定化させて脚の代謝負担を抑えます。
15〜21kmの江の島折返し前後
応援密度が高く心拍が上がりやすい区間。折返しで風向きが変わると体感が急変するため、折返し前後はフォーム確認(肘角・骨盤・接地位置)をルーチン化して乱れを即時補正します。
| 区間 | 想定ペース | ポイント |
|---|---|---|
| 0〜5km | 目標+5〜10秒/km | 渋滞回避と酸素負債ゼロ |
| 5〜10km | 目標±0〜+3秒/km | 呼吸とピッチの同期 |
| 10〜15km | 目標±0秒/km | 補給準備とフォーム点検 |
| 15〜21km | 目標+0〜+5秒/km | 折返し直後の再整流 |
- 最初の給水は混雑回避のため位置を1つ遅らせる選択肢
- 折返し前にジェル1本を早めに摂取し復路へ備える
- ピッチは序盤180前後で安定化を目安に
- 肩の力みを抜くため5km毎に脱力チェック
- 上半身の前傾角の過不足を動画化イメージで補正
- ジグザグをしないライン取り
- 追い風区間でも心拍は閾値未満を死守
- 給水は被るのではなく飲む優先
- 靴紐やウェアの微不快は早期に解消
- 沿道の声援で加速しすぎない
提案:前半は「楽に速く」を合言葉に、感覚より遅い時計表示を良しとするメンタル設計が有効です。
後半22〜42kmの区間攻略
後半は風と疲労への対処が鍵です。特に30km以降は西湘バイパス復路で風の影響が強まり、ピッチ低下と腰落ちが同時に発生しがち。意識すべきは「接地の真下化」「肘を後ろに引く」「踵骨を臀部へ近づける」の3点。これにより前傾角を維持し、空気抵抗を増やさず推進力を保てます。
22〜30kmの耐える区間
グリコーゲン消費が進むため、等張〜やや高張のジェルと電解質の並行摂取で血糖を安定化します。風が強い日は同等ペースの集団に付く意思決定を早め、単独走を避けます。
30〜37kmの西湘バイパス復路
最もタフなセクション。ラップが落ちても焦らずフォームの質を守り、歩幅よりピッチで調整。橋・ランプの短い登りは腕振りを強め、骨盤を前に送る意識で失速を最小化します。
37km以降のフィニッシュまでの押し切り
ゴールまでの数キロは筋損傷が進んだ脚での技術勝負。上体の脱力と足関節のバネを使い、地面反力を前方向へ逃がす。イーブンに近い呼吸に戻せれば再加速も可能です。
| 区間 | 対風戦略 | 補給 |
|---|---|---|
| 22〜27km | 集団に付き負荷一定化 | ジェル+電解質少量 |
| 27〜32km | 肩甲帯の脱力で抵抗減 | カフェイン系の選択可 |
| 32〜37km | ピッチ優先で登り凌ぐ | 蜂蜜系で粘度低い物 |
| 37km〜 | 腕振り強調で推進維持 | リキッド系で喉通り優先 |
- 風に正面を向けず僅かに斜め姿勢で当てる
- 踵接地が増えたら重心を1cm前に置く意識
- 下りは骨盤主導で接地時間を短縮
- 痙攣兆候には電解質とピッチアップで対応
- ラップより主観負荷の一定化を優先
- 30km手前で補給を終える段取り
- 寒風時はグローブで末梢冷え対策
- 帽子のツバで視界と体幹の安定
- ジェル廃棄はポーチ管理でマナー厳守
- 最後の3kmは呼吸でリズム制御
覚書:後半は「守って伸ばす」。フォームと呼吸の質を守れば、結果的にタイムは伸びます。
ペース設計と関門対策
制限時間は6時間30分の想定。複数の関門が設定されるため、早見表で「最低限の通過ライン」を把握し、向かい風や混雑を織り込んだ配分を組みます。基本は微ネガティブ(後半同等〜+10秒/km)を軸にし、向かい風が強い日は前半の微貯金(総量で60〜90秒)で吸収します。
目標タイム別の配分
サブ3.5〜サブ6までの代表配分を示します。いずれも前半で心拍閾値未満を死守し、30km以降の風・起伏での落ち幅を最小化する設計です。
向かい風時の体力管理
出力一定(主観負荷一定)で進むのが基本。時計のペース低下に反応して無理に合わせるよりも、体力温存で終盤の押し返しを狙います。
ネガティブスプリットの可否
風が弱い日や曇天の低気温では十分可能です。江の島折返し後の復路で心拍を保ったまま5秒/kmの微加速を狙い、二宮折返しからの微アップダウンで守り切るイメージを持ちましょう。
| 関門地点 | 距離目安 | 閉鎖時刻目安 |
|---|---|---|
| 平塚八間通り入口 | 約5.1km | 10:10 |
| 茅ヶ崎公園 | 約10.8km | 10:56 |
| 辻堂海浜公園西側 | 約14.2km | 11:24 |
| 中部バス駐車場 | 約19.2km | 12:03 |
| 辻堂海浜公園東側 | 約21.9km | 12:25 |
| 相模川左岸処理場 | 約28.3km | 13:17 |
| 大磯港IC | 約35.0km | 14:13 |
| 大磯西IC | 約37.1km | 14:29 |
| 西湘二宮IC | 約39.6km | 14:55 |
- 前半の貯金は最大でも+90秒に制限
- 風が強い日は「時間」より「心拍」を優先管理
- 関門表を手首に貼り最低ラインを共有
- 失速兆候はピッチ+3で早期是正
- 最後尾回収バスの存在を前提に余裕度を持つ
- サブ3.5:前半1:44後半1:46の微ネガティブ
- サブ4:前半1:58後半2:02を目安
- サブ5:各5km30分を刻む均等配分
- 完走狙い:関門+3〜5分の安全マージン
- 気温上昇時は+5〜10秒/kmで体温管理優先
補足:関門時刻や配置は大会毎に変更があり得ます。エントリー要項の最新版を必ず確認してください。
給水・補給とトイレ戦略(マイボトル前提)
本大会はマイボトル・マイカップ運用が基本です。手元給水は混雑回避と摂取量の安定化に優れますが、携行重量と落下リスクも伴います。ボトルの固定方法、補給食の相性、トイレの位置と混雑ピークを事前に決めておくことで、大きなタイムロスを防げます。
マイボトル給水の実際
500mlを2分割(250ml×2)で携行し、5km毎に2〜3口ずつのスモールシップで体内の浸透を優先します。エイドの給水スタンドは予備・補充ポイントとして活用します。
補給食のタイミング
15km・25km・35kmを基準にジェル等を配置。胃腸に負担が出る寒冷条件では粘度の低いリキッドタイプが有効です。電解質は早め早めの分割投与を徹底します。
トイレ・混雑回避の目安
スタート前は会場最奥の列が意外と回転が速い傾向。レース中は公園前の仮設付近で偏りやすく、手前の仮設へ早めに寄る選択が待機時間短縮につながります。
| 項目 | 推奨 | 理由 |
|---|---|---|
| ボトル容量 | 250ml×2 | 重量分散と落下リスク低減 |
| 電解質 | ナトリウム300〜500mg/時 | 痙攣・低ナトリウム対策 |
| ジェル | 15/25/35km | 血糖安定と終盤対策 |
| トイレ | 混雑手前で早決断 | 待機ロスの最小化 |
| 携行方法 | ベルトorベスト | ブレ低減と手振りの自由 |
- スタート30分前に200ml摂取で初動を軽く
- 等張濃度のドリンクを優先して吸収促進
- 胃もたれ時は水で希釈し粘度調整
- 寒冷時は温存のため糖質摂取間隔を詰める
- 携行品は左右均等配置で骨盤のブレ抑制
- ボトルはソフトフラスクで安全性向上
- 予備のミニカップで緊急補水に対応
- エイドの位置は事前に地図で把握
- 手袋は滑り止め付きで扱いやすく
- 捨てポーチでゴミの持ち帰り徹底
注意:マイボトル運用は事前練習が必須。本番だけの携行は落下や腹部圧迫の原因になります。
アクセス・試走・当日チェックリスト
会場へはJR東海道線の大磯駅・二宮駅からのアクセスが一般的で、当日はシャトル運行が組まれます。早朝はバス待機列が長くなることがあるため、集合時刻は余裕を持って設定しましょう。試走は風向きの確認に最適で、実線路面の傾斜や橋梁のリズムも体感できます。当日は寒風対策と手元補給、待機中の保温が優先事項です。
会場アクセスとシャトル
行きは早便のシャトルで余裕を確保し、帰りは更衣・受け取り動線を把握してから列へ。交通規制の範囲と時間帯は前週の告知を必ずチェックします。
試走と風向きの確認
前週〜前日に短時間でも海岸線でジョグを行い、風向きと強度を身体で掴んでおくと当日の配分判断が速くなります。追い風体感のコツ、向かい風のピッチ維持を実地で確認しましょう。
当日の装備と持ち物
低気温・海風・長時間待機に備え、ウェアは可変レイヤリングを採用。スタート直前に脱げるディスポのアウター、耳まで覆えるキャップや軽量手袋が有効です。
| 項目 | 推奨 | 備考 |
|---|---|---|
| アクセス | 早便シャトル利用 | 列のピーク回避 |
| 試走 | 5〜8kmの確認走 | 風と起伏の体感 |
| 装備 | レイヤリング | 待機冷え対策 |
| 補給 | ボトル+ジェル | 携行は左右均等 |
| 復路 | 合流地点の動線確認 | 渋滞回避 |
- 前日受付やゼッケン確認を早めに完了
- 会場導線と手荷物預けの位置を事前把握
- 試走で風と橋のリズムを体に刻む
- 朝食はスタート3時間前に消化良い内容で
- 関門表と緊急連絡先を携帯へ保存
- 使い捨てアウターで待機中の保温
- 帰路の防寒具をゴール近くに確保
- スマホ充電と交通系ICを事前準備
- 集合写真やトイレの時間を逆算
- パーソナルベストより安全完走を優先
ヒント:試走は「風の授業」。当日の判断を素早くし、配分迷いを減らします。
まとめ
湘南国際マラソンのコースは、フラット基調かつ景観に恵まれた一方で、海風と単調さがパフォーマンスを左右する戦略型のレイアウトです。前半は渋滞と高揚をかわしながら「楽に速く」を徹底し、折返し後の向かい風に備えて体力と集中力を温存。
後半はピッチとフォームの質を優先し、橋・ランプは腕振りで押し、ネガティブに近い配分で押し切ります。関門時刻の最低ラインを把握し、マイボトル運用と補給の段取りを整えておけば、完走確率は大きく上がります。アクセス動線と当日の保温・装備まで含めて「準備8割」で臨み、湘南の海と富士の眺めを味方に、あなたのベストへと繋げてください。