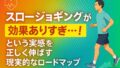- 平均と中央値の違いを把握し1km設定を誤らない
- サブ6〜サブ3までの換算を一望できる早見表
- 距離帯ごとの失速ポイントと対処の型
- 高低差や暑熱など外的条件の補正係数の考え方
- 練習指標(LT・MP)から導く妥当な1kmペース
フルマラソンの平均タイムを1kmペースで理解する
まずは「平均」「中央値」「目標タイム」と1kmペースの関係を整理する。平均は外れ値の影響を受けやすく、中央値は集団の中心を示す。市民ランナー全体像では中央値が実感に近い。
たとえば完走者の中心が5時間前後なら、1kmあたりは約7分06秒の巡航となる。ここに年齢や性別、コース難度、気象のバイアスが重なるため、実戦では±5〜10秒/kmの揺らぎを前提とするのが安全だ。
完走者の中央値と平均の違いを押さえる
中央値は「半数がそれより速く半数が遅い」速度であり、練習計画や当日の初期設定に適する。一方、平均は完走時間の分布が長い尾を持つため遅い側に引かれやすい。初マラソンの設定は中央値寄りで、2回目以降は自己データに基づき補正すると再現性が上がる。
年代別男女別のおおよその基準値
年代が上がるほど最大酸素摂取量と回復力が低下するため、同一トレーニングでも1kmペースは緩む傾向にある。男女差は体格と筋量の影響が主で、個人差が大きい。ここでは厳密値でなく「相場」を押さえ、無理のない設定幅を守ることが重要だ。
目標サブ6〜サブ3の換算と注意点
サブ6からサブ3までの代表的な換算は後述の表が把握を助ける。注意点は、下り基調や追い風など「たまたま速い条件」で得た練習ラップをそのまま採用しないこと。基準はフラット換算で決め、条件が悪い日は追加で安全マージンをつける。
測定とラップ管理の基本
GPS時計の自動ラップは便利だが、トンネルや高層街で乱れる。1km標識での手動ラップを併用し、体感・呼吸・接地音の変化を同期させる。ペースは「見に行く」のでなく「保つ」ものだ。
1km基準で見た疲労の推移
筋グリコーゲン枯渇や筋損傷は30km以降に顕在化する。1kmラップが5〜8秒/1kmずつドリフトするなら補給不足や冷却不足が疑われる。
| 目標タイム | 平均1kmペース | 時速(km/h) |
|---|---|---|
| 6時間 | 8:32/km | 7.0 |
| 5時間 | 7:07/km | 8.4 |
| 4時間 | 5:41/km | 10.5 |
| 3時間30分 | 4:58/km | 12.1 |
| 3時間15分 | 4:37/km | 13.0 |
| 3時間 | 4:16/km | 14.1 |
- 中央値ベースで初期設定
- 条件差を±5〜10秒で補正
- 自動と手動ラップの二重化
- 呼吸接地の主観指標を同期
- 補給と冷却の計画を先に決める
- 平均と中央値の目的を分けて使う
- 1km標識での実測を重視する
- フラット換算で基準化する
- 安全マージンは序盤に多め
- 疲労ドリフトの兆候を早期検知
目標別の1kmペース早見表と換算のコツ

目標から逆算する方法はシンプルで再現性が高い。ここでは完走(サブ6相当)からサブ3までの代表値をまとめる。実際の設定では気象と高低差、給水ロスを織り込み、レース当日は−3〜−5秒/kmで入り過ぎないことが鍵だ。
完走〜サブ6を安全に刻む設定
初マラソンや完走重視は、呼吸会話可能な強度で巡航し、給水ポイントでの減速を見越して平地は一定。下りで稼がず、上りで粘る。
サブ5〜サブ4の巡航を作る
巡航期の体温・心拍を安定させるため、給水直後のラップ上振れを許容し全体の平均を整える。補給は30分毎に少量高頻度で。
サブ3.5〜サブ3の精密管理
LT直下の強度での巡航は補給と体温管理に失敗すると急失速する。周囲の集団に巻かれず自分の指標で押す。
| 区分 | 代表タイム | 平均1kmペース |
|---|---|---|
| 完走重視 | 6:00:00 | 8:32/km |
| サブ5 | 5:00:00 | 7:07/km |
| サブ4.5 | 4:30:00 | 6:24/km |
| サブ4 | 4:00:00 | 5:41/km |
| サブ3.5 | 3:30:00 | 4:58/km |
| サブ3 | 3:00:00 | 4:16/km |
- 目標タイムを先に決める
- 上表から基準ペースを引く
- 気象と高低差で±補正
- 給水ロスを事前に計上
- 入りは控えめに
- 補給は時計アラームで固定化
- 集団の波に乗り過ぎない
- 下りで稼がずフォーム優先
- 上りはストライドよりピッチ
- 信号や折返しのロスを想定
距離帯ごとの落ち込みやすさと対策
マラソンは42.195kmを均一に走る競技だが、実際は距離帯ごとに身体負担の主因が変わる。ここを理解せずに一定ペースを盲信すると、30km以降に一気に帳尻が合わなくなる。
0〜10kmの立ち上がりと心拍安定
スタート直後は興奮と混雑で過不足が出やすい。冷静に心拍を上げ過ぎず、呼吸整合で巡航域に入れる。
10〜30kmの巡航維持と補給設計
糖と脂質の配分、体温上昇のコントロールが鍵。水分と電解質の不足は脚攣りの引き金になる。
30km以降の失速対策と歩かない工夫
筋損傷の影響が顕在化するフェーズ。フォーム保全と補給の継続が最重要だ。
| 距離帯 | 起こりやすい課題 | 1km対策の要点 |
|---|---|---|
| 0〜10km | 突っ込み過ぎ | 目標より+3〜5秒で静かに入る |
| 10〜20km | 体温上昇 | 給水直後は−3秒の上振れ許容 |
| 20〜30km | 補給不足 | 30分毎に糖質と電解質 |
| 30〜42km | 筋ダメージ | ピッチ微増で接地を軽く |
- 心拍の立ち上げは緩やかに
- 補給は高頻度少量で固定
- 冷却は給水ごとに実施
- 30km以降はフォーム優先
- 歩かずに短いジョグで繋ぐ
- 整列は適正ブロックを厳守
- 混雑では無理に抜かない
- 下りでストライドを出し過ぎない
- 痙攣兆候に早めの電解質
- 応援に乗って上げ過ぎない
コース条件と気象が与える平均ペース補正

同じ能力でもコースと気象で1kmあたりの妥当値は変わる。レース選びや当日の作戦では、フラット換算を基準に補正を積み上げるのが合理的だ。
高低差風路面での実質負荷
登坂は筋持久と心肺に、下りは筋損傷に効く。向かい風は体感以上に消耗する。
気温湿度WBGTの補正と暑熱対策
暑熱は体温・心拍・脱水に同時圧をかける。寒冷時は筋の伸張性低下でケガリスクが増す。
混雑給水ロスを織り込む
参加規模が大きい大会は給水ロスが累積しやすい。動線とキャパを事前に把握し、取りやすい側に寄る。
| 条件 | 推奨補正 | 備考 |
|---|---|---|
| 登り多い | +3〜8秒/km | 序盤は控えめ |
| 強い向かい風 | +5〜10秒/km | 集団活用 |
| 気温20〜25℃ | +3〜6秒/km | 冷却強化 |
| 気温25℃超 | +8〜15秒/km | 完走重視 |
| 混雑・狭路 | +2〜5秒/km | 線形損失 |
- フラット換算の基準を持つ
- 当日気象で補正幅を決める
- 風向きをコース図で確認
- 給水動線を事前把握
- 補正後の入りラップをメモ
- 登りはピッチ増で腰高を維持
- 下りは接地を軽く制動最小
- 風は隊列でやり過ごす
- 暑熱は氷水スポンジを活用
- 寒冷は手袋と露出抑制
練習指標から決める妥当な1km設定
レース前の練習データから妥当な1kmペースを決めると、過大評価と過小評価の両方を避けられる。鍵はイージー(E)、乳酸閾値(LT)、マラソンペース(MP)の関係だ。Eは回復と土台、LTは持久力の上限、MPは本番の巡航域を示す。
イージーとLTの役割
イージーは会話可能で呼吸が乱れない強度。LTはややきついが持続可能なギリギリの強度で、ここを押し上げるとMPが安全に速くなる。
マラソンペースMPの決定プロセス
直近6〜8週間のロング走とLT走の結果から、フラット換算での巡航値を決める。練習で10〜15kmを無理なく維持できるペースがMPの中核になる。
テーパリングで仕上げる
大会2〜3週前から総量を落とし、強度は部分的に維持。睡眠と栄養で疲労を抜き、体内リソースをレース日に集中させる。
| 指標 | 1kmの体感 | 目的 |
|---|---|---|
| E | 楽に会話可 | 回復と基礎 |
| MP | やや余裕 | 本番巡航 |
| LT | きついが維持 | 上限引上げ |
| ロング | 後半に負荷 | 持久性獲得 |
- 6〜8週の練習を棚卸し
- フラット換算でMP仮決め
- 30km走で検証し微修正
- テーパリングで疲労抜き
- 当日補正を前夜に確定
- 週1のLT走で上限更新
- E走は会話基準を守る
- ロングは補給練習を兼ねる
- 坂道や向かい風で筋力補強
- 睡眠と体重管理を徹底
レース当日の運用術とラップ管理
当日は練習で決めた基準を「実行に落とす」工程だ。ラップは時計の数字ではなく戦術の結果であり、ネガティブスプリットを基本に設計する。
ネガティブスプリットの作り方
前半は目標より+3〜5秒/kmで入り、体温と心拍が安定したら目標に合わせ、終盤は余力で−3秒を狙う。無風区間や下りでのみ微加速する。
給水給食のタイミング実践
30分ごとに糖質、15〜20分ごとに水分と電解質。暑熱時は冷却もセットで行う。胃腸の耐性は練習で作っておく。
ガジェット設定と手動ラップ
自動ラップと手動ラップの二重化、アラートはペースと心拍の上下限を設定。トンネルや高層街では手動が頼りだ。
| 局面 | 基準 | 運用メモ |
|---|---|---|
| 前半 | +3〜5秒/km | 人と風に乗らない |
| 中盤 | 目標±0秒 | 給水直後は上振れ許容 |
| 終盤 | −3秒/km | 下りと無風で微加速 |
| 暑熱 | +8〜15秒/km | 完走最優先 |
- 入りを抑えて後半勝負
- 補給は時計アラームで固定
- 心拍上限を越えない
- 手動ラップで実測補正
- 条件悪化時は即時再設定
- 整列位置は実力相応
- 給水は奥側を狙う
- ジェルは早めに口へ
- 痙攣兆候は歩かずピッチ維持
- 応援区間でも上げ過ぎない
まとめ
1kmあたりの平均タイムは「現在地の把握」「目標の可視化」「当日の運用」を一気通貫でつなぐ強力な指標だ。平均と中央値を使い分け、目標から逆算した基準をフラット換算で決め、気象や高低差、混雑や給水ロスを積み上げて補正する。
距離帯ごとの課題に合わせて初動の突っ込みを抑え、中盤は補給と冷却で安定を作り、終盤はフォームを保って小さく上げる。練習期にはE・LT・MPの三本柱を整え、直近6〜8週間の実績から再現性のあるMPを決定する。
レース当日はネガティブスプリットを基本に、自動と手動のラップ二重化で数値の信頼性を確保し、心拍や主観強度と同期させる。最終的に重要なのは、数字を崇拝することではなく、数字を状況に合わせて運用する態度である。表とリストを用いた本稿の枠組みを、自身のコンディションと大会条件に当てはめ、無理のない設定で納得の一日を作ってほしい。