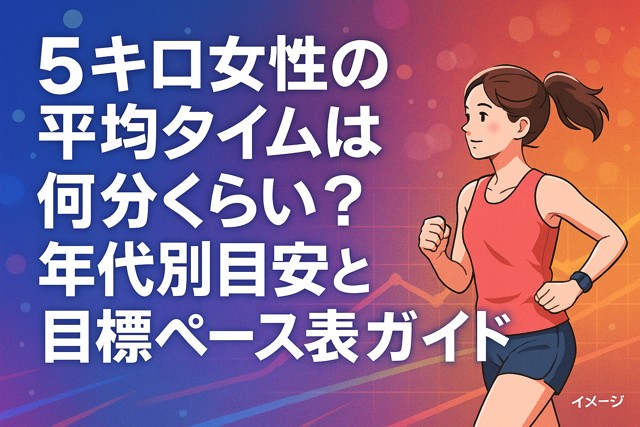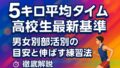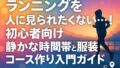まずは自分に合う基準を選び、無理なく継続できるラインから一段ずつ引き上げていきましょう。
- 対象読者
- 初完走〜30分切りを目指す女性ランナー
- 得られること
- 年代別・走力別の現実的レンジと練習指標
- 使い方
- 表のレンジ→配分→練習→当日運用の順に適用
- ペース表は「目安」。体調やコースで±数%の揺れを見込む
- 強度は週内で波をつける。高強度の翌日は必ず軽め
- 色文字の注意は失速リスクが高い要点を示す
女性の5km平均タイムの基準(年代別と走力別)
平均タイムは「一般的な到達レンジ」を示す統計的な目安で、個人差を大きく受けます。
ここでは年代別と走力レベル別に幅を持たせた目安を提示します。はじめは幅の中でも余裕が残るゾーンを採用し、3〜4週間同水準で安定したら次の幅へ進むのが安全です。
年代別の目安レンジ
以下は練習経験がある程度ある女性ランナーの「完走から記録更新を狙う」層を想定したレンジです。未経験〜運動再開直後は+3〜6分程度の余裕を見込みましょう。
| 年代 | 健康維持層の目安(5km) | 走り込み層の目安(5km) |
|---|---|---|
| 10代 | 24〜32分 | 20〜26分 |
| 20代 | 25〜33分 | 21〜27分 |
| 30代 | 26〜34分 | 22〜28分 |
| 40代 | 27〜36分 | 23〜29分 |
| 50代 | 29〜38分 | 24〜31分 |
| 60代 | 31〜41分 | 26〜34分 |
走力レベル別の目安レンジ
自己申告の体感でおおよそ次のレベルに分け、レンジを選びます。
- 入門:完走重視。目安は35〜45分
- 初級:週2〜3で練習。目安は30〜35分
- 中級:ポイント練あり。目安は25〜30分
- 上級:継続的な高強度。目安は20〜25分
- 再起:ブランク明け。直近1か月は入門の上限+α
初心者が最初に狙う現実的なライン
最初のゴールは「無理なく完走→40分切り→35分台安定」の順。完走段階ではウォークブレイクを入れてもよく、心拍や呼吸が落ち着くことを優先します。
記録向上の幅と停滞期の見極め
5kmの伸び幅は4〜8週間で1〜3分が目安。寝不足・暑熱・連続高強度が重なると停滞・逆行が起きやすいので、週単位で負荷の波を設けましょう。
タイム測定と自己評価のやり方
- 平坦で交通量の少ないコースを固定
- ウォームアップ10〜15分+流し
- 3km地点の通過で配分を再評価
- 終了後に主観強度(RPE)と平均ペースを記録
- 同条件で2〜4週間ごとに再測定
目標タイム別の配分とラップ計算

同じゴールタイムでも配分次第で体感は大きく変わります。5kmは短距離寄りの有酸素イベントで、基本は「前半やや抑えて後半じわ上げ」。ここでは主要な目標タイムに対する1kmペースの目安を示し、ネガティブスプリットの簡単な作法と、失速の典型パターンをまとめます。
40分から25分までの1kmペース表
| 目標タイム | 1kmペース(分:秒/km) | 目安ラップ配分 |
|---|---|---|
| 40:00 | 8:00 | 8:05→8:05→8:00→7:55→7:55 |
| 37:30 | 7:30 | 7:35→7:35→7:30→7:25→7:25 |
| 35:00 | 7:00 | 7:05→7:05→7:00→6:55→6:50 |
| 32:30 | 6:30 | 6:35→6:35→6:30→6:25→6:25 |
| 30:00 | 6:00 | 6:05→6:05→6:00→5:55→5:50 |
| 27:30 | 5:30 | 5:35→5:35→5:30→5:25→5:20 |
| 25:00 | 5:00 | 5:05→5:05→5:00→4:55→4:50 |
ネガティブスプリットの使い方
- 目標ペースを決める(表を起点に±5秒の幅)
- 1〜2kmは目標+5〜10秒で入り呼吸を整える
- 3km通過で主観強度をチェックし−5秒まで引き上げ
- 4kmはフォームとピッチを維持し横風時は隊列を活用
- 残り500mは腕振り先行で腰高を維持しスパート
タイムが落ちる原因と修正ポイント
- 突っ込みすぎ:序盤+15秒/km抑制を徹底
- 心拍高止まり:給水とピッチ上げでストライド過多を修正
- フォーム乱れ:肘角度と目線を固定し着地音を静かに
- 風・勾配:集団背後・峠は復路で取り返す計画を
- 暑熱:日陰と散水を活用し帽子内側を冷却
Q:時計なしでも配分できる? A:会話テストで「短文がギリ言える」を維持すれば目標+5〜10秒/kmの入りに近づきます。
週3で伸ばす練習メニュー設計
無理なく継続するために、週3本(ポイント2+つなぎ1)を基本に据えると回復と刺激のバランスがとりやすくなります。仕事や家事の波に合わせて入れ替え可能なテンプレを用意し、各回に明確な狙いを持たせましょう。
ビルドアップ走の頻度と強度
呼吸と心拍のコントロールを覚える最適解。3〜6kmのビルドアップを週1回。
- 1km=目標+20秒/km
- 2km=目標+10秒/km
- 3km=目標ペース
- 4km以降=−5秒/kmで維持(余力があれば)
- ダウンジョグ10〜15分
インターバルとレペの組み立て
スピード耐性を上げる日。合計距離は3〜4kmを目安に。
- 400m×6〜8本(R=200mジョグ)=5km目標−10〜15秒/km
- 1000m×3〜4本(R=2〜3分)=目標−5〜10秒/km
- 流し×4〜6本で脚の可動域を確保
つなぎジョグと完全休養の配分
疲労管理の要。RPE4〜5の快適ペースで30〜50分。眠気・重だるさ・脈の高止まりが出たら完全休養へスイッチ。
- RPE
- 主観的運動強度。0〜10で自己管理
- レペ
- 短距離の反復走。フォーム重視で全力ではない
- VO2max
- 最大酸素摂取量。上げ急がず土台作りが先
- 失敗:毎回全力→回避:目的に合わせ刺激を分散
- 失敗:距離稼ぎ優先→回避:質の確保を先に
- 失敗:同じコース固定→回避:勾配や路面を変え刺激
- 失敗:補給軽視→回避:朝はバナナや小さなゼリー
- 失敗:睡眠不足→回避:高強度前夜は+1時間
心拍と呼吸で管理する安全基準

数字は便利ですが、最終的な安全性は体感と呼吸が守ります。時計がなくても活用できる「会話テスト」、心拍ゾーンの目安、過負荷のサインを押さえておきましょう。
RPEと会話テストの活用
- RPE4〜5:短文が自然に話せる=ジョグ域
- RPE6〜7:息は上がるが会話は断片的=テンポ走域
- RPE8:単語がやっと=インターバル域
- RPE9〜10:会話不可=ピーク刺激は短時間のみ
- 胸痛・めまい・しびれがあれば即中止
ゾーン別の目安と上げ下げの判断
| ゾーン | 感覚の目安 | 用途 |
|---|---|---|
| Z1〜Z2 | 楽に会話可 | 回復・土台作り |
| Z3 | 短文で会話 | 持久力向上 |
| Z4 | 単語のみ | 乳酸耐性・テンポ |
| Z5 | 会話不可 | 最大刺激は短時間 |
オーバートレーニング回避のサイン
朝の安静時心拍が平常+5以上、階段で妙に苦しい、眠りが浅い、脛や膝の違和感が続く——いずれかが2日連続で出たら強度を一段落とすサイン。1週間はビルドアップを外し、Z1〜Z2中心で立て直すのが賢明です。
| 方法 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 心拍ベース | 客観指標で再現性 | 暑熱や脱水で変動 |
| RPEベース | 道具不要で即実践 | 慣れるまでブレ |
Q:更年期で体調が揺れる時は? A:Z1〜Z2中心に切り替え、週の合計時間を7〜8割に調整。症状が落ち着いたら徐々に復帰します。
体格と環境とコース条件の補正
同じ努力でも条件が違えばタイムは揺れます。体格(体重)、気温・湿度、風や勾配、路面の硬さ、生理周期など、代表的な変動要因の影響を目安化しておきましょう。
体重と気温湿度で変わる所要時間
| 体重(kg) | 概算消費エネルギー(5km) | 暑熱時の配分目安 |
|---|---|---|
| 45 | 約225kcal | 基準+10〜15秒/km(25〜28℃) |
| 50 | 約250kcal | 基準+15〜20秒/km(30℃前後) |
| 55 | 約275kcal | 基準+20〜30秒/km(高湿度) |
| 60 | 約300kcal | 基準+30秒/km超(直射・無風) |
勾配風路面の影響を見積もる
- 上り1%=体感で+10〜20秒/km、下り1%=−5〜15秒/km
- 向かい風3〜5m/s=+10〜25秒/km、追い風は体感軽減
- 芝や砂利は+10〜30秒/km、トラックは−5〜10秒/km
生理周期とコンディショニング
周期によって体温や浮腫み、睡眠の質が変わります。違和感が強い週はZ1〜Z2に寄せ、レース週と重なる場合は目標を「完走」「後半じわ上げ」へ柔軟に再設定します。
事例:都市公園の5km——前半が向かい風で後半が追い風。行きで+10秒/km抑え、帰りで−10〜15秒/kmの取り返しを計画するだけで体感が大きく改善します。
レース当日の戦略と装備一覧
直前の迷いを減らし、当日は淡々と実行するだけに。ウォームアップ〜スタート〜3kmの分岐〜ゴール後まで、使い回せる手順と装備の定番をまとめます。
ウォームアップとスタート運び
- ジョグ10分+動的ストレッチ
- 流し80〜100m×4本で心拍を上げる
- 列の並びは目標タイム帯の後方寄り
- 1kmは目標+5〜10秒で呼吸を整える
- 2〜3kmでフォームとピッチの確認
補給水分シューズの最適解
- 気温20℃超:スタート15〜20分前に少量給水
- シューズ:足幅と用途優先。反発よりも安定とフィット
- ウェア:風向きに合わせ前面を簡易防風
- 携行品:ゼッケン留め・小袋・薄手キャップ
- 時計:オートラップ1km・心拍アラートは任意
ゴール後の回復と次の目標設定
ゴール直後は歩行で心拍を落とし、水分と糖質を少量ずつ。夜にRPE・区間ペース・体調メモを残し、翌日以降の練習を調整。次の目標は「同条件で−15〜30秒」から。調子が波打つ時は過去ベストとだけ比較しないことが継続のコツです。
Q:雨の日は走る? A:短時間なら可。体温低下を避けるためスタート前の待機を短くし、帽子と吸水の少ないソックスを選びます。
まとめ
「5キロ何分女性」「5キロ平均タイム女性」という問いの答えは、年代と走力と条件の三つで決まります。まずは年代別・レベル別のレンジから現在地を見つけ、目標ペース表で配分を可視化し、週3のメニューで安全に積み上げます。
心拍と呼吸を使った自己監視で過負荷を避け、体格や気象・コースの補正を前提に「同条件での比較」で成長を測りましょう。レース当日は手順どおりに淡々と実行し、結果はRPEや区間ごとの体感メモとセットで評価。今日の一歩が次の−15〜30秒につながります。無理をせず、安定して走れるゾーンから一段ずつ進めていきましょう。