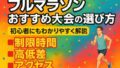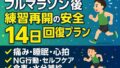- 1km・5km・10km・ハーフの通過目安
- 週2ポイント+ロング走の設計
- 気象補正・補給・装備の最適化
2時間40分の基準ペースと到達目安
フルマラソン2時間40分は、平均ペースおよそ3分48秒/km(安全圏の目安として3分47秒/km)で42.195kmを走り切る実力を指します。10kmやハーフの実力、閾値(LT)と最大酸素摂取系(VO2max)の両面が高水準でまとまっており、「スピードはあるが失速する」「距離は踏めるが伸びない」という片寄りでは届きません。
ここでは、通過目安・スプリット・VDOT相当・練習ペース帯を具体化し、現状地図を描けるようにします。レースではGPS誤差やライン取りのロスが生じるため、公式目標3:48/kmに対し「体感3:47/km」を普段から刻む習慣を持つと再現性が高まります。
スプリット(5kmごと)と主要通過タイム
| 通過 | 目安タイム(3:47/km基準) | レース中の着眼点 |
|---|---|---|
| 5km | 18:55 | 呼吸と接地リズムの均一化、混雑回避で脚を使い過ぎない |
| 10km | 37:50 | ピッチ/ストライドが安定しているか、補給導入タイミングの確認 |
| 15km | 56:45 | 微風向・勾配の影響を平均化、上下動のムダを抑える |
| 20km | 1:15:40 | フォーム弛緩の再点検、足裏と股関節の連動を意識 |
| ハーフ | 1:19:40〜1:19:50 | 体感余裕度を1段残す、後半起点のネガティブ構成を温存 |
| 30km | 1:53:30 | 補給/水分の確実化、股関節〜腸腰筋の張りを早期解放 |
| 35km | 2:12:25 | フォームの「前で回す」意識へ移行、接地時間を僅かに短縮 |
| 40km | 2:31:20 | 上半身の脱力で腕振りを軽く速く、呼吸で心拍の暴れを抑制 |
| Finish | 2:39台後半〜2:40:00 | ラスト2kmは姿勢と腕振りのリズム維持を最優先 |
VDOT相当と練習ペース帯の目安
- 目安VDOT:およそ60〜62(個人差あり)
- R(レペティション):2:58〜3:05/km(200〜400m)
- I(インターバル):3:12〜3:18/km(800〜1200m)
- T(閾値走):3:35〜3:40/km(20〜40分)
- M(マラソン):3:47〜3:52/km(10〜24km)
- E(イージー):4:40〜5:10/km(回復〜積上げの主役)
到達の現実解:10km・ハーフの目安
- 10km
- 35分30秒前後を安定して切れると見通しが立つ
- ハーフ
- 1時間16分台〜1時間17分台で、巡行時に余裕度を残せること
環境補正の考え方
| 条件 | 補正の目安 | 対応 |
|---|---|---|
| 気温20〜24℃ | +3〜5秒/km | 目標を3:50/kmに再設定、補給と水分を早めに |
| 気温25℃以上 | +7〜12秒/km | 完走最優先、前半を抑えて後半判断 |
| 向かい風 3〜5m/s | +2〜4秒/km | 隊列活用、フォームは前傾を僅かに強める |
2時間40分に近づく練習設計

週2回のポイント練習(スピード×スタミナ)にEランの量を重ね、月間で質と量の双方を確保します。最短距離で伸ばす鍵は「閾値の底上げ」「Mペースの巡行耐性」「脚づくり(腱・筋膜)」の三層構造です。
スピード偏重や距離偏重の片寄りでは、30km以降の落差で帳消しになりがちです。練習は常に「次のブロックで積み替え可能か」を基準に設計し、疲労の窓口(ふくらはぎ・中臀筋・腸腰筋)をケア前提で閉じていきます。
ポイント練は週2:スピード×スタミナの二軸
- スピード軸(I/R):1000m×5〜6(r=200mジョグ)@3:12〜3:18/km、または400m×10〜12 @3分/km感覚
- スタミナ軸(T/M):T20〜30分一本、もしくはM16〜24km(後半ビルド)
- 隔週で「ロングビルド走」:28〜35kmの中盤からM寄りへ移行
Eペースの「量」が仕上がりを決める
Eは心拍・筋ダメージを抑えて酸素運搬能力と腱の耐久を養う「土台」です。週4〜5回、40〜70分のEを淡々と積むことで、ポイント練の回復も早まります。ペース幅は体調で揺らして構いませんが、上下動・接地時間・重心移動は一定を守ります。
ロング走の型(3種類)
- 距離走:30〜35km @E〜M-15秒/km(脚つくりと補給の訓練)
- 時間走:2時間〜2時間30分(地脚の維持と姿勢課題の洗い出し)
- ロングビルド:前半E、後半Mへスライド(実戦の再現)
補助ドリルと筋力の底上げ
- 流し(100m×6〜10):接地時間短縮と可動域の維持
- ヒルスプリント(6〜10本):出力×腱の張力を安全に刺激
- 補強(週2):中臀筋・腸腰筋・ハム・足底をルーチン化
ブロック設計例(4週)
| 週 | ポイント① | ポイント② | ロング | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I:1000m×6 @3:15 | T:25分 @3:37 | 30km @E | 翌週に向けE多め |
| 2 | R:400m×12 @3:00感 | M:20km @3:50→3:47 | 28km ビルド | 流しを週2で |
| 3 | I:1200m×5 @3:17/km | T:30分 @3:38 | 35km E寄り | 補給パターン検証 |
| 4 | 調整:1000m×3 @5km感 | M:16km @3:48 | 120分E | 回復と積み替え |
週間スケジュールの実例
生活・仕事の制約下で持続可能な設計に落とし込むことが最重要です。ここでは「基本週」「強化週」「回復週」の3バリエーションを提示します。ポイントの質を担保しつつ、Eランと補強を欠かさず回し、睡眠・栄養・体重管理までをパッケージで運用します。週の前半でスピード、後半でスタミナに寄せ、週末ロングで仕上げる流れが安定します。
基本週(仕事繁忙期に適合)
| 曜日 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 月 | E60分+流し×6 | 前週の疲労抜き |
| 火 | I:1000m×5〜6(r200m) | 可動域ドリル前置き |
| 水 | E70分+補強20分 | 骨盤周りを重点 |
| 木 | T:20〜25分 | 心拍を閾値域で維持 |
| 金 | オフ or E40分 | 睡眠優先デー |
| 土 | E50〜60分+流し | 翌日に疲労を持ち越さない |
| 日 | ロング30km(後半ビルド) | 補給実験と姿勢管理 |
強化週(余裕のある週に当てる)
- 火:R 400m×12 @3:00感 + 坂流し×6
- 木:M 20〜24km(後半3:47/kmへ)
- 日:35km E〜M-15秒/km(補給を本番同等)
回復週(3〜4週に1回)
- ポイントは1回のみ(T15〜20分)
- Eラン中心、合計走行距離を20〜30%落とす
- 睡眠+栄養+整体orセルフリリースで回復優先
朝夕二部練の使い分け
- 朝E+夕補強
- 代謝と体重コントロールが容易、走行距離の確保に有効
- 朝流し+夕I/T
- 神経活性→質練で出力を引き出す構成
レース戦略と補給

2時間40分の鍵は「序盤の余裕度」「中盤の均一化」「終盤の微上げ」の三段構えです。前半のオーバーペースは35km以降の失速に直結します。
補給は60〜75g/時の炭水化物を軸に、カフェインのタイミング、ナトリウム補給、水分量をプラン化。天候・風・高低差に応じたラップの揺らぎは許容し、平均化の目で管理します。
序盤〜中盤のラップ運用
- 0〜5km:3:49〜3:51/kmで流入、渋滞は回避するが抜きすぎない
- 5〜20km:3:48/kmに収束、向かい風や橋は数秒の貯めで吸収
- ハーフ通過:1:19:40〜1:19:50で余裕1段残し
- 20〜35km:補給と姿勢維持で均一化、地味に数秒の貯金を作る
- 35km〜Finish:腕振りテンポ↑、呼吸で心拍を整え3:47/kmへ
補給計画(例:2時間40分想定)
| 地点 | 内容 | 狙い |
|---|---|---|
| 5km | ジェル1(炭25g)+水 | 血糖低下の予防、消化負担の少ない序盤導入 |
| 10km | ジェル1(炭25g)+スポドリ | 糖+電解質の同時補給で安定 |
| 15km | 水のみ or うがい | 胃の余裕を保つ、小休止 |
| 20km | ジェル1(炭25g、カフェイン少量)+水 | 中盤の覚醒とリズム回復 |
| 25km | スポドリ | 発汗量に応じて口数を調整 |
| 30km | ジェル1(炭25g)+水 | 終盤のガス欠予防 |
| 35km | ジェル1(必要に応じ追加) | 最後の伸びを作るブースト |
暑熱・風対策と装備の微調整
- 気温20℃超:3〜5秒/kmのマージン、首元・腋下の冷却を活用
- 向かい風区間:肩の力を抜き、前傾角を僅かに深めて接地時間短縮
- 雨天:ソックスは薄手・撥水、シューズ紐は二重結び
テーパリング(2週間)
- T-14〜8日:走行距離70〜80%、T15〜20分を1回、M10〜12kmを1回
- T-7〜4日:走行距離50〜60%、刺激(1000m×3)でキレ維持
- T-3〜0日:E30〜40分+流し、睡眠と糖質寄りの食事にシフト
シューズ・時計・体重管理
装備は「再現性」を高めるための道具です。厚底カーボンは推進効率を引き上げますが、脚づくりが不十分だと腱・足底に反動が出ます。時計はペースだけでなくピッチ・ストライド・接地時間・上下動を計測し、フォームの数値化に活用。体重は1kgあたりフルで約2〜3分の影響とも言われ、ピーク体重へ「緩やかに」近づける運用が肝要です。
シューズの使い分け
| 用途 | 推奨タイプ | 狙い |
|---|---|---|
| レース/MP走 | 厚底カーボン(反発強) | 巡行効率と後半の脚保護 |
| T/I/R | 反発中〜強のトレーナー or 軽量レーサー | 出力を引き出しつつ故障抑制 |
| E/ロング | クッション重視+安定 | 回復促進と腱の負担軽減 |
GPSウォッチの活用ポイント
- 自動ラップは1km固定+手動ラップで区間管理
- 表示は「平均ラップ」「ピッチ」「ストライド」を優先
- 上り下りは心拍の揺れで確認、ペースに固執しすぎない
体重・栄養の運用
- 目標体重
- レース2〜3週前にピークへ、直前は維持を優先
- 平日
- タンパク質1.6〜2.0g/kg、炭水化物は練習量で可変、脂質は質重視
- 前日〜当日
- 低残渣+高糖質へ寄せ、当日は固形を早めに切り上げて液体中心
よくある失敗と壁の突破法
2時間40分を阻む典型は「前半の数秒オーバー」「補給遅れ」「フォームの崩れ」「メンタルの硬直」です。いずれも30〜35kmで表面化し、ラップが一気に10秒以上落ちます。突破には、練習で「崩れの予兆」を拾い、対策ルーチンを身体に刻むこと。特効薬はありませんが、積み上げの質を1つずつ最適化すれば、終盤で自然と“落ちない身体”が現れます。
35kmの失速を防ぐチェックリスト
- 前半の最速ラップは3:45/km以内に留める(風・坂での暴走禁止)
- 15kmまでに2回は糖+電解質を通す(胃に優しい少量多回)
- フォーム合言葉:「背中で押す・肩を落とす・肘は後ろへ」
- 脚が重いときはピッチ+2〜3spmで「小さく速く」
停滞期の打破:短距離とトラックの処方
- 1500m/3000mに挑戦:スピードの天井を上げるとTが楽になる
- 200m/300mレペ×8〜12本:接地時間と設置角を研ぎ澄ます
- 400mHのドリルを拝借:腰高維持と上体の安定に効く
故障予防とケアの基礎
| 部位 | 兆候 | 対策 |
|---|---|---|
| アキレス腱 | 朝の違和感、押圧痛 | ヒールドロップ、厚底の使用頻度調整、冷感→温感の順で |
| 足底 | 踏み出し時の刺す痛み | 足底リリース、タオルギャザー、路面選択 |
| 腸脛靭帯 | 外側の張り〜痛み | お尻系の補強(中臀筋)、下りの負荷管理 |
メンタル運用:意思決定を事前に固定
レース中の判断を「もし〜なら〜する」のIF集で事前に固定します。例えば「25kmで脚が重ければ、ピッチ+2spm・腕振りテンポ↑・次の給水で一口多め」。揺らぎをなくすほどパフォーマンスは安定します。
まとめ
2時間40分は、閾値の底上げと有酸素の量、そして適切な補給で掴めます。3分47秒/kmのペース感を軸に、週2の質とEペースの積み上げ、30km以降の失速対策を徹底しましょう。大会選び・体重管理・厚底活用まで漏れなく整備することが近道です。
- 今週:T走20分/Mペース16km/L走30km
- 今月:10kmかハーフのTTで現状確認
- 本番:5kmごとの補給と体温管理を徹底