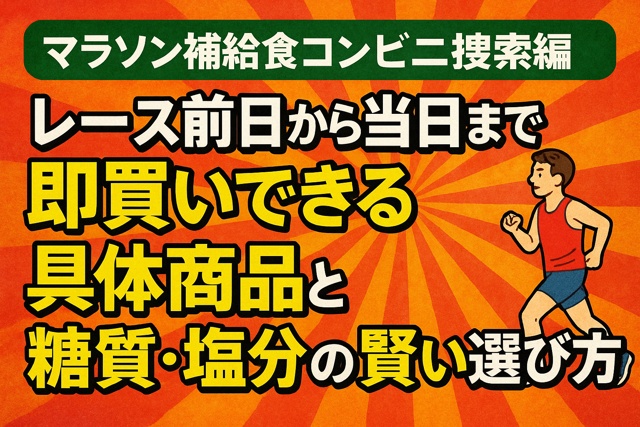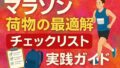- 距離別の糖質目安と摂取タイミング
- セブン・ファミマ・ローソンで買える具体商品
- 胃腸にやさしい組み合わせと避けたい食品
コンビニで揃う補給食の基本
「マラソン 補給食 コンビニ」のキーワードが示す通り、レース当日の補給はコンビニ調達だけで十分に成立します。要点は、(1)消化に優しく、(2)運びやすく、(3)距離と気温に応じて糖質と電解質の比率を最適化すること。ようかん・ゼリー・バナナ・おにぎり・和菓子・スポーツドリンク・塩飴など定番の中から、自分の胃腸に合うものを練習で試し、当日は「量と間隔」を機械的に再現します。迷いを排し、補給を“習慣化された作業”に落とし込むことが、30km以降の粘りを生みます。
何を選ぶか(ようかん・ゼリー・バナナ・おにぎり)
基本は糖質が主で脂質と食物繊維が少ないもの。ようかんはポケットに収まり、寒い日でも硬化せずに咀嚼しやすいのが利点。ゼリー飲料は水分と糖質を同時に摂れ、暑熱時に相性が良い。バナナはカリウムを含み脚つり対策の一助になり得ますが、皮の処理や携行性の観点で一口サイズに分けるなどの工夫が必要。おにぎりはスタート前~序盤のゆっくり区間で有効ですが、脂質の多い具は避けます。
避けたい食品(高脂質・高食物繊維)
- 揚げ物・クリーム系パン:消化遅延と胃もたれの原因。
- ナッツ・雑穀バー:繊維と脂質が多く、個体差はあるがリスクが高い。
- 冷たすぎる乳飲料:気温や体質により下痢を誘発することがある。
- 人工甘味料の多い飲料:浸透圧の関係で腹部不快感を起こす場合がある。
糖質量とカロリーの目安
フルマラソンでは走力にもよりますが、体内グリコーゲンだけに頼らず、5kmごとに糖質20〜30gを目安に追加し、合計で150〜250g程度の糖質補給を想定します。摂取の粒度は細かいほど胃腸に優しく、血糖の上下動を抑えやすくなります。
| 食品例 | 1個あたり糖質 | エネルギー | 携行性 | 想定タイミング |
|---|---|---|---|---|
| ミニようかん | 20〜25g | 90〜120kcal | 高(小型・常温安定) | 5〜10kmごと |
| ゼリー飲料(エネルギー系) | 25〜45g | 100〜200kcal | 中(ややかさばる) | スタート前/10km/25km |
| バナナ(半分) | 10〜15g | 40〜60kcal | 低〜中(形崩れ注意) | スタート前/前半 |
| おにぎり(小) | 35〜45g | 150〜200kcal | 低(序盤限定) | ウォームアップ〜5km |
塩分・ミネラル補給の考え方
発汗量が多いランナーは、糖質だけでなくナトリウム500〜700mg/時程度(目安)をスポドリ・塩飴・タブレットなどで分割補給すると安定します。汗で失われるカリウム・マグネシウムも微量ながら意識すると脚つりの抑制に寄与します。
カフェインの可否と注意点
カフェインは主観的なきつさを和らげ、終盤の集中を助けますが、胃腸が敏感な人は刺激になることがあります。カフェイン入りゼリーやタブレットを使う場合は、練習で必ず試す、水分を一緒に摂る、空腹に大量投与しない、を徹底します。
メモ:補給は「種類」より「タイミングと総量」が重要。自分の消化速度に合わせて、細かく刻んで同じリズムで入れる。
レース前日の準備と当日朝のコンビニ活用

前日から当日朝までの動線が整っていれば、補給は8割成功。コンビニで買える定番を「数」と「順番」まで落とし込み、スタート会場までの移動中に迷いをゼロにします。前日は炭水化物中心、脂質と繊維は控えめ、当日は起床〜スタートの時間幅に応じて量を微調整します。
前日の買い出しリスト
- ミニようかん ×3〜5本(5〜10km刻み用)
- ゼリー飲料 ×2〜3個(スタート前/25km/非常用)
- 塩飴 or 電解質タブレット ×1袋(暑熱時は多め)
- スポーツドリンク1本(500〜600ml)+水1本(500ml)
- 朝食用:おにぎり2個 or バナナ1本+カステラ/どら焼きなど
- 予備:使い慣れたエネルギーバー(低繊維タイプ)
- 小分け用ミニ袋・輪ゴム・紙テープ(携行の固定用)
当日朝の消化に優しい補食
起床がスタートの3時間以上前なら、固形の炭水化物も取りやすい。2時間前を切る場合はゼリー中心で胃負担を下げます。
| 残り時間 | 目安メニュー | 糖質量目安 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 3時間前 | おにぎり1〜2個+水 | 70〜90g | 脂質少なめの具を選ぶ |
| 2時間前 | カステラ/どら焼き+スポドリ | 40〜60g | 固形はよく噛んで量を控えめに |
| 60〜30分前 | ゼリー飲料1個 | 25〜45g | スタート直前の空腹を避ける |
| 15分前 | ミニようかん1本+数口の水 | 20〜25g | 血糖の初動を安定させる |
水分・電解質の仕込み
- ボトルにスポドリを用意(暑い日はスタート前に200〜300ml、小分けで)
- 塩飴/電解質タブレットをウエストポーチに2〜4個セット
- ジェルは落下防止のため吸い口を紙テープで補強、切り込みを入れて開封容易に
ヒント:会場付近のコンビニは混雑するため、宿泊地や乗換駅で先に購入し、当日は“補充のみ”にする。
スタート〜30kmの補給プランと携行方法
補給は「決めたリズム」を守ることが命。ペースが上がっても下がっても、5kmごとに糖質20〜30gを目安に自動実行します。給水所では“飲む→入れる→流す”の三拍子で詰まりを防ぎ、携行品は左右均等に配置し揺れを減らします。気温・風・雨で発汗量が変わるため、塩分は状況に合わせて追加します。
補給タイミングと間隔
| 区間 | 糖質目安 | 推奨アイテム例 | 水分/塩分 |
|---|---|---|---|
| スタート直前 | 20〜25g | ミニようかん | 水を数口 |
| 0〜10km | 20〜30g×2回 | ゼリー1、ようかん1 | 給水所で100〜150ml/回 |
| 10〜20km | 20〜30g×2回 | ようかん2 or ゼリー1+ようかん1 | 塩飴1個(暑熱時) |
| 20〜30km | 20〜30g×2回 | ゼリー1+ようかん1 | スポドリ優先で給水 |
| 30km以降 | 20〜25g×1〜2回 | 終盤用ジェル/ようかん | 脚つり感なら塩タブ追加 |
ポーチ・ポケットの収納術
- 左右対称に配置してバランスを取る(例:ようかん左2本・右2本)
- ジェルは吸い口を下向きに、走行中でも片手で開けられるよう切り込みを事前に
- 汗で紙包装が弱るため、ラップや小袋で耐水対策
- ごみは二重袋にまとめ、フィニッシュ後に捨てる(コース上のポイ捨て厳禁)
暑熱・寒冷時のアレンジ
| 条件 | アレンジ | 注意点 |
|---|---|---|
| 暑熱(最高気温20℃超) | ゼリー比率↑、スポドリ主体、塩飴/電解質を1時間に1〜2個 | 甘味疲労に備え、和菓子系を1本混ぜる |
| 寒冷(体感10℃未満) | ようかん比率↑、温かいお茶で口直し(スタート前) | 水分摂取忘れに注意、給水で必ず数口 |
| 雨・風強 | 包装の耐水補強、幟や向かい風区間で固形は避ける | 手がかじかむ場合は開封補助をさらに工夫 |
ルール:苦しくても“次の給水所で20g入れる”。例外は胃痛や嘔気のみ。迷いを排して自動化する。
セブン・ファミマ・ローソンで買える具体例

大手3社の棚構成は似ています。和菓子(ようかん・わらび餅)、ベーカリー(カステラ・薄皮あんぱん系)、フルーツ(バナナ)、ゼリー飲料、飴・タブレット、ドリンク(スポドリ・水)が基本。銘柄は変わっても“選ぶ基準”が同じなら代替が利きます。以下はコンビニでよく見かけるカテゴリー別の使い分け例です。
セブンで買うなら(羊羹・わらび餅・ゼリー飲料)
- ミニようかん:小型で割れにくく、ポケット管理が容易。
- わらび餅(少量パック):暑熱時の口直しに適し、喉通りが良い。
- ゼリー飲料:終盤の一発逆転よりも“計画的な一口ずつ”に活用。
ファミマで買うなら(カステラ・バナナ・ゼリー飲料)
- カステラ/どら焼き:前日〜当日朝の炭水化物源として安定。
- バナナ:カリウム補給の一助。半分にしてラップで包むと携行しやすい。
- ゼリー飲料(カフェイン入りの選択肢がある場合):練習で相性確認のうえ終盤用に。
ローソンで買うなら(バランス栄養食・ナッツ・和菓子)
- バランス栄養食(低繊維タイプ):移動中の補食に。レース中は量を控える。
- 塩飴・タブレット:汗が白く乾くタイプは多めに持つ。
- 和菓子小分け:ようかん代替。甘味の質を変えて飽きを防ぐ。
| カテゴリー | 糖質/個 | 食塩相当量 | 形状 | 携行性 | 推奨タイミング |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニようかん | 20〜25g | 微量 | 固形小型 | ◎ | 5〜10km刻み |
| ゼリー飲料 | 25〜45g | 0.1〜0.3g | 半流動 | ○ | スタート前/中盤/終盤 |
| バナナ(半分) | 10〜15g | 微量 | 固形 | △ | スタート前〜序盤 |
| おにぎり(小) | 35〜45g | 0.5〜1.0g | 固形 | △ | ウォームアップ時 |
| 塩飴/電解質 | — | 0.1〜0.2g/個 | 固形 | ◎ | 暑熱時に1時間1〜2個 |
コツ:銘柄が変わっても「糖質20〜30g/回」を満たす量で置き換える。棚替えに動じない“基準の目”を養う。
胃腸トラブル・低血糖を避けるコツ
最も多い失敗は「練習で試さない」「まとめ食い」「甘味の単調化」の3つ。胃腸は鍛えれば順応します。週末ロング走で本番どおりのタイミング・同じ銘柄・同じ量を繰り返し、腸を“教育”するイメージで備えます。低血糖の“寒気・ふらつき・ネガティブ思考”が出る前に、ルーチンで入れておくのが鉄則です。
練習での事前テスト
- ロング走(20〜30km)で5kmごとに20〜25gを摂取し、胃の張り・げっぷ・腹鳴をチェック
- 甘味の種類(和菓子/ゼリー/ドリンク)をローテーションして飽きを抑制
- 暑い日と寒い日で水分量を変え、トイレリスクと脚つりリスクのバランスを調整
食べ合わせと水分のバランス
| 組み合わせ | 相性 | 理由/注意 |
|---|---|---|
| ようかん+水(数口) | ◎ | 浸透圧負担が少なく咀嚼も容易 |
| ゼリー+スポドリ | ○ | 糖質+電解質。過剰な一気飲みは避ける |
| バナナ+牛乳 | △(前日まで) | 当日は人によっては下す可能性、試走が前提 |
| おにぎり+濃いコーヒー | △ | カフェイン感受性により胃刺激・利尿が強まる |
コンビニ食品の原材料チェック
- 脂質が5gを超えるものは当日用から外す(前日夜までに)
- 難消化性デキストリンなど食物繊維強化はレース中は避ける
- 人工甘味料の多用は腹部膨満の原因になりうるため注意
サインを見逃さない:寒気・手先の震え・集中低下は低血糖の兆候。予定より早くても20g追加して立て直す。
フィニッシュ後の回復食とリカバリー
完走直後の30分は“栄養のゴールデンタイム”。ここで糖質とタンパク質を同時に入れると回復が早まり、翌日の疲労感が明確に変わります。コンビニなら、甘味+乳製品+水分・電解質の三点セットが最短ルートです。固形が入らないときはドリンクやヨーグルトで代替し、体温が下がっている場合は温かい飲料で内臓を労わります。
30分以内の糖質+タンパク質
| 組み合わせ | 糖質/タンパク質目安 | ポイント |
|---|---|---|
| どら焼き+プロテインドリンク | 40〜60g / 20〜25g | 咀嚼で満足感、吸収も良い |
| 大福+飲むヨーグルト | 40〜50g / 10〜15g | 乳酸菌で胃の落ち着きも期待 |
| ゼリー飲料(高糖質)+牛乳 | 45〜60g / 8〜12g | 固形が入らない時の代替 |
乳製品・プロテインの使い分け
- 胃腸が弱い人:低脂肪乳やヨーグルトで量を分割
- すぐ移動する人:紙パック/ペットボトルのプロテイン飲料で手早く
- 固形も行ける人:おにぎり+プロテインでグリコーゲンと筋修復を同時に
塩分・ビタミンでリカバリー
- スポドリでナトリウム補充を継続、脚つり感があれば軽く塩飴を追加
- フルーツカップやバナナでビタミン・カリウムを補い、利尿で失ったミネラルを戻す
- 温かいお茶やスープで体温を戻し、消化を助ける
| タイムライン | 行動 | 目安量 |
|---|---|---|
| T+0〜30分 | 糖質+タンパク質、スポドリ少量ずつ | 糖質40〜60g+タンパク質10〜20g |
| T+60〜90分 | 軽食(おにぎり/サンド)と水分 | 糖質50〜70g+タンパク質15〜25g |
締め:回復は“すぐ・分割・温める”。コンビニの組み合わせで充分に実現できる。
まとめ
失速を防ぐ鍵は、練習で試した補給を当日も再現すること。基本は5kmごとに糖質20〜30g+こまめな水分と塩分。コンビニの定番を賢く組み合わせ、気温や体調に応じて微調整すれば30km以降も粘れる。前日から買い忘れ防止のメモを用意しよう。