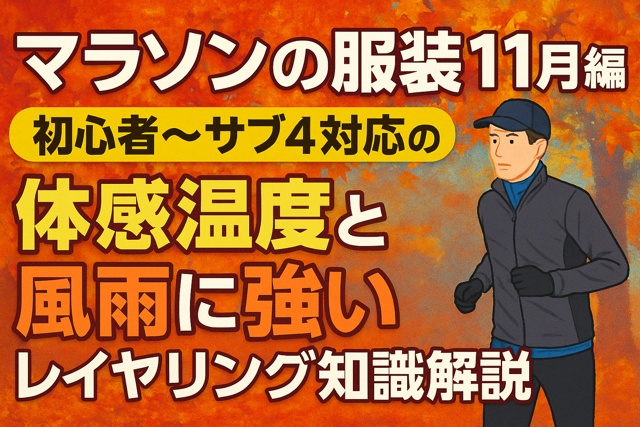- 0〜5℃/6〜10℃/11〜15℃の装備テンプレ
- 初心者〜サブ4の走力別レイヤリング調整
- 雨・風・晴れの天候別ポイントと汗冷え対策
11月マラソンの気温目安と服装選びの基本
11月は「朝の冷え込みとレース中の発熱」が拮抗しやすい時期。スタート待機では指先や耳が冷え、走り出すと5〜10分で体温が上がり、20〜40分で汗が衣服内に滞留しやすくなります。
したがって、厚着で安心を取りに行くよりも、発汗後の汗冷えを最小化する「吸汗速乾+防風で熱を逃がし過ぎない」組み合わせが軸になります。さらに、都市型レースではビル風の突風や橋上区間の強風、郊外レースでは放射冷却による体感低下が起きやすく、同じ気温でもコース環境で体感は大きく変化します。
服装の判断は「気温だけ」でなく、風速・日射・降水の有無、そして自分の走力(発熱量)を掛け合わせるのが鉄則です。迷ったら、アームカバーや薄手シェルなど「走りながら外せる保険」を1枚足し、オーバーヒート時に即座に調整できる可変性を確保してください。
気温と体感の関係を掴む
体感温度は、気温から風と湿り気(雨・汗)で大きく変わります。風速が1m/s上がるごとに体感は下がり、濡れた生地は気化冷却でさらに熱を奪います。
11月は大会の号砲が早朝〜午前であることが多く、日が高くなる前は特に風の影響が強く出る傾向。たとえば気温10℃でも北風が強ければ「6〜7℃相当」に、雨が加われば「3〜5℃相当」まで体感が落ちるイメージです。逆に無風・日射ありなら、走行時の発熱で「15℃相当」の装いが快適になることもあります。
| 実測気温 | 風・雨の条件 | おおまかな体感 | 基本方針 |
|---|---|---|---|
| 0〜5℃ | 無風・乾燥 | 0〜3℃ | 防風最優先。薄手保温+シェル。 |
| 6〜10℃ | 微風・乾燥 | 5〜8℃ | 長袖中心。脱着できる小物で微調整。 |
| 11〜15℃ | 無風・日射あり | 13〜18℃ | 半袖+アームで可変。通気重視。 |
| 6〜10℃ | 北風強め | 3〜6℃ | 前面防風。耳・指先を保護。 |
| 10〜12℃ | 小雨 | 5〜8℃ | 撥水+汗処理。濡れ対策と擦れ防止。 |
走力別に変える「ちょうど良い」厚み
同じコーデでも、発熱量の高いランナーは暑く、ゆっくり走るランナーは寒く感じます。目安として、サブ4前後は「半袖+アーム」や「薄手長袖」で十分な場面が多く、完走狙い・歩き混じりの想定があるなら「長袖+薄手ベスト」や手袋で保険を追加。待機時間が長い大会では「使い捨て防寒(ポンチョ・カイロ)」でスタート直前まで体温を温存し、号砲と同時に外す運用が効果的です。
- 迷ったら「軽くて脱げるもの」を1点追加
- 前面は防風、背面は通気で汗の滞留を減らす
- 汗冷えを防ぐためベースは必ず吸汗速乾
- 待機・走行・ゴール後の「3局面」を別々に考える
スタート前・レース中・ゴール後の温度差対策
寒暖差は失速や体調不良の原因です。スタート前は冷えを避けるため「保温>軽量」を優先し、記録狙いでも胴体を冷やさないこと。レース中は逆に「通気>保温」に切り替え、風区間や橋上だけ薄手シェルで前面を守る。ゴール後は汗が冷えて一気に体感が下がるため、保温ジャケットと乾いたドライT、厚手ソックスを素早く着替え、飲食で内側からも温める準備をしておきましょう。
気温別コーディネート(0〜5℃・6〜10℃・11〜15℃)

気温帯ごとに「最初は少し寒い」くらいで出るのがセオリー。走り出して10〜15分で体が温まり、ちょうど良くなれば成功です。ここでは気温帯別に、トップス・ボトムス・小物の組み合わせをテンプレ化し、実走で微調整しやすい優先順位を示します。なお同じ気温でも風や雨があれば一段階“下の帯”として扱い、前面防風や撥水を追加してください。
0〜5℃:防風シェル+薄手保温で冷えを遮断
最も辛いのはスタート待機と前半の橋上区間、川沿い区間。胴体の前面だけでも風を止められる薄手シェルは強力な味方です。保温は「分厚いフリース」ではなく、薄手の起毛長袖やミッドウェイトのベース。走り出しに暑ければ前を開け、落ち着いたらウエストに巻く想定で、収納しやすい軽量素材が便利です。下半身はフルタイツや膝周りの軽いサポートタイツ、擦れ対策のバームを併用すると快適性が上がります。
- トップス:薄手起毛長袖+超軽量防風シェル
- ボトムス:ロングタイツ or ショーツ+ロングカーフ
- 小物:薄手手袋・耳まで覆うビーニー・ネックゲイター
- スタート待機:使い捨てポンチョ+貼るカイロ(走行直前に外す)
6〜10℃:長袖ベース+アーム・ベストで調整幅を確保
多くの11月レースが該当。序盤は長袖、ペースが上がる中盤で暑くなればアームを下ろす、風が強ければ薄手ベストを羽織るといった細かな操作がしやすい帯です。迷うなら「長袖+アーム+薄手ベスト」を基本パッケージにしておくと安心。下半身はショーツ+軽量レッグスリーブまたは7〜9分丈の薄手タイツで、膝の保温と可動域を両立します。
- トップス:長袖ドライ+アームカバー(脱着で微調整)
- ボトムス:ショーツ+軽量スリーブ or 薄手タイツ
- 小物:薄手手袋・軽量キャップ・サングラス(乾燥対策)
- 前面のみ防風:胸〜腹部をカバーするベストが有効
11〜15℃:半袖中心で通気優先、日射・汗冷えに注意
半袖+ショーツが基準。スタートが冷え込む場合に備えてアームカバーと軽量手袋を持ち、5km前後で外す運用が最もスムーズです。汗はしっかり出る温度帯なので、吸汗速乾の性能差が出ます。背面の通気・脇下の放熱・生地の肌離れを重視し、レース中盤〜終盤の粘りを損なわない軽さを選びましょう。
| 気温帯 | トップス | ボトムス | 小物の要点 |
|---|---|---|---|
| 0〜5℃ | 起毛長袖+防風シェル | ロングタイツ | 耳・首・指の保温を最優先 |
| 6〜10℃ | 長袖ドライ+ベスト | ショーツ+スリーブ | 風区間のみ前面防風 |
| 11〜15℃ | 半袖+アーム | ショーツ | 汗処理と日射対策を両立 |
いずれの帯でも「序盤に軽く寒い」を合格ラインとし、オーバーヒートの兆候(顔が火照る、手先が熱い、脇が蒸れる)を感じたら優先して放熱。逆に寒気を感じたら、走りを緩めずに小物で前面を覆うか、風上側だけアームを上げるなど、ピンポイントで調整しましょう。
レイヤリングの考え方(ベース・ミッド・アウター)
レイヤリングは「汗を素早く離すベース」「熱を抱え過ぎず循環させるミッド」「風雨を制御するアウター」の三位一体。11月は汗量が適度に発生するため、どこか1枚でも役割を外すと、汗戻りや冷えでパフォーマンスが落ちます。ポイントは“厚さ”より“材質”と“配置”。前面は防風、背面は通気、脇は放熱、首元は調節幅が広い構造だと、同じ重量でも快適性が段違いに向上します。
吸汗速乾ベースレイヤーの選び方
ベースは肌離れと拡散力が命。フィットは「密着し過ぎず、余りすぎず」で、汗を点で受けて面に拡げる生地が理想です。縫い目が肩や脇に当たると擦れやすいので、フラットシーマーやボンディング仕様を選ぶと安心。迷ったら軽量メッシュ or 格子状の起毛で、体幹は保温、脇や背中は放熱というメリハリを作りましょう。
| 素材 | 強み | 注意点 | 11月向け目安 |
|---|---|---|---|
| ポリエステル | 速乾・軽量・耐久性 | 汗戻りしやすい製品も | 通気設計のモデルを優先 |
| ポリプロピレン | 疎水性で肌離れ抜群 | 静電気・耐熱弱め | 寒冷帯のインナーに好適 |
| ウール系 | 調湿・防臭・温かい | 厚手はオーバーヒート | 薄手ブレンドで汗冷え抑制 |
ミッドレイヤーは「保温し過ぎない」ことが鍵
ミッドは“空気の層”を作る役目ですが、厚すぎると汗が滞留。起毛でも短毛・薄手を選び、前面の密度はやや高く、背面や脇は通気を優先。ハーフジップは放熱バルブとして優秀で、上げ下げで微調整が容易です。さらに、袖や裾が“風でバタつかない”フィットだと、わずかな風でも体感が安定します。
アウターは「前面の風を切り、背面で逃がす」
フル防風は確かに温かいですが、11月のフルマラソンではオーバースペックになりがち。前面は防風、背面はパネルで通気、という“前後非対称”の設計がベストバイ。雨が想定される場合は「撥水軽量シェル」を第一選択にし、土砂降り確定でもなければフル防水は避けるのが無難です。重さ・透湿・携行性のバランスが取れた100〜150g級のウインドシェルが使い勝手に優れます。
- ベース:肌離れ重視、縫い目は擦れにくい構造
- ミッド:薄手起毛 or 通気ニット、ハーフジップで調整
- アウター:前面防風・背面通気、携行しやすい軽量設計
よくある失敗と解決策
「寒いのが怖くて厚着」→前半は快適でも中盤以降に汗冷えし失速。解決は“脱ぎやすさ”優先で、アームや前開きシェルを採用。「ベースが綿混」→濡れて冷える。解決はドライ素材へ。「フル防水で蒸れる」→内側が結露。解決は撥水軽量シェル+防水キャップなど局所防御。細部では、襟元の肌当たり・袖口の密着・裾のずり上がり抑制など、走行時の動きに合わせたディテールが快適性を大きく左右します。
小物で微調整(手袋・アームカバー・ネック)

11月の服装戦略を“完成”させるのは小物です。体幹は温かくても、末端が冷えると集中を欠き、フォームが崩れ、補給も疎かになりがち。手首・指・耳・首は「小さな投資で大きなリターン」が得られる部位です。軽くて脱着が容易、ポケットや腰で携行できる小物を選び、気温や風に応じて素早くオン・オフして体感温度を狙い通りに保ちましょう。
手袋・アームカバーの使い分け
手袋は「薄手ドライ」を基本に、風が強ければニットやウインドブレークの甲当てで補強。汗で濡れると一気に冷えるため、速乾性の高い生地を選ぶこと。アームカバーは、スタート時に上げ、中盤で下ろし、風区間や橋上で再び上げるなど、細かな調整が効きます。親指ホール付きは手の甲の保温にも有利で、手袋と併用すれば体感を数℃押し上げられます。
| 小物 | 役割 | おすすめの使い方 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 手袋 | 末端保温・風除け | 薄手速乾+甲のみ防風で軽快 | 濡れたら交換 or 携行で調整 |
| アーム | 体幹の近くを可変保温 | 橋上・向かい風で上げる | 締め付け過多は循環低下 |
| ネック | 気化冷却の制御 | 序盤だけ使用→熱くなれば外す | 厚すぎは息苦しさの原因 |
| ビーニー/イヤー | 耳の保温 | 風区間のみ装着 | 発汗後は早めに外す |
ネックゲイター・ビーニーの活用と落とし穴
首元は動脈が浅く、保温効果が体感に直結します。ネックゲイターは薄手を選び、鼻まで上げれば風切り音も軽減。ビーニーは耳を覆える浅被りタイプが走行に向きます。ただし、どちらも“暑くなったらすぐ外す”こと。汗を含んだまま着け続けると、風が当たるたびに一気に体感が下がり、終盤の失速に繋がります。
スタート前だけの「使い捨て防寒」
スタート待機が長い大会では、軽量ポンチョや古Tなどを上から羽織り、号砲直前で脱ぎ捨てる運用が有効です。体幹が冷えると交感神経が優位になり、心拍が上がって無駄に体力を消耗します。「走り出せば温まる」は正しい一方で、「走り出すまでは冷やさない」を徹底することが、当日のメンタルと身体の安定につながります。
- 小物は「携行しやすさ」「片手で調整しやすい」を最優先
- 寒気を感じたら“末端から”覆うと効率的
- 汗を含んだ小物は早めに外して汗冷えを予防
天候別の対策(晴れ・雨・風)
同じ11月でも、晴れ・雨・風で戦略は大きく変わります。晴天は汗処理と日射対策、雨天は濡れと擦れの管理、強風は前面防風と露出コントロールが核。気象は刻々と変わるため、装備は「組み替え前提」で用意し、当日の現地コンディションで最終決定するのが賢明です。
晴天:汗冷え・日差し対策と補給
日射があると体幹の温まりが早く、半袖+アームで充分なことが多くなります。汗が増える分、塩分と水分の補給計画を忘れず、キャップとサングラスで目と頭部を守ると集中力が保てます。背面がフルメッシュのトップスや、脇下のベンチレーションがあるモデルは、終盤の粘りに効きます。日差しが強い都市部では、路面からの照り返しで体感が上がるため、黒一色の重い生地よりも淡色・軽量の生地が快適です。
雨:撥水・防水の限界と体温管理
小雨なら撥水シェルで十分。大雨確定でも、フル防水は透湿不足で内側が結露しやすく、レースでは重くなりがちです。現実的には、帽子のツバで顔面の雨粒を避け、前面だけ撥水、背面は通気という“濡れにくく蒸れにくい”設計が総合点で優位。乳首や内腿、脇は擦れやすくなるため、ワセリンや専用バームを広めに塗り、ソックスは厚すぎず、濡れても肌離れが良いタイプを選びます。雨で手がかじかむと補給が難しくなるので、タブ開封しやすい手袋や、パッケージを事前に切り込み加工するなどの工夫が効きます。
風:前面防風と露出コントロール
風は体感を最も下げる要因です。向かい風セクションは前面の露出を減らし、ジッパーを上げて顎・首元まで風を遮断。追い風や風の当たらない街区ではすぐに開けて放熱に切り替えます。橋上・海沿いは想像以上に冷えるため、薄手の防風ベストやアームの上げ下げで数分単位の微調整を繰り返すのが効果的。風の音で集中が切れないよう、耳当てや薄手ビーニーを短時間使うのも有効です。
| 天候 | 装備の核 | 追加の工夫 | 避けたい失敗 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 半袖+アーム+通気トップス | キャップ・サングラス | 厚手で蒸れる重装備 |
| 雨 | 撥水軽量シェル+擦れ対策 | ツバ付きキャップ・速乾小物 | 重量級フル防水で蒸れる |
| 風 | 前面防風ベスト or シェル | 橋上のみ耳当て・首元強化 | 露出多めのまま我慢 |
- 当日の気象で直前に組み替えられる“選択肢”を持つ
- 風・雨は前面を守り、背面は常に逃がす設計
- 擦れ対策は「脇・内腿・乳首・足指」を忘れない
タイツ・ショーツ・ソックス・シューズの選び方
下半身の快適性は、ピッチの維持と着地の安定に直結します。11月は筋温が下がり過ぎるとスムーズな振り出しが阻害され、逆に厚着で蒸れると肌トラブルが発生。タイツ・ショーツ・ソックス・シューズを「保温・通気・擦れ・重量」の4軸で捉え、自分の走力とレース時間に合わせて最適化しましょう。
タイツ/ショーツの使い分けと擦れ対策
ロングタイツは保温と筋振動の抑制に有効ですが、厚すぎると発汗後に不快。11月は薄手〜中厚のサポートタイツか、ショーツ+レッグスリーブの“分割保温”が扱いやすい選択です。ショーツ派は、インナーの縫い目や股擦れ対策を優先し、シームレスやボンディング仕様を。クリームやバームはスタート30分前に十分量を塗布し、雨予報なら追加の小分けを携行すると安心です。
| ボトムス | 利点 | 弱点 | 11月向けの使いどころ |
|---|---|---|---|
| ロングタイツ | 保温・振動抑制 | 発汗後の蒸れ | 0〜8℃、橋上・風区間が多いコース |
| ショーツ+スリーブ | 可変性・軽快 | 膝の保温に工夫が必要 | 6〜12℃、アップダウンや橋が点在 |
| 7〜9分丈 | 膝保温と通気の折衷 | 丈が合わないと擦れ | 8〜13℃、都市型コースに好適 |
ソックスの厚み・丈・素材の基準
濡れや汗冷えに強いのは、肌離れの良い化繊系やウールブレンドの薄〜中厚。丈はシューズの履き口と擦れない高さを確保し、ふくらはぎスリーブを使うなら重なり部位の圧が過度にならないよう注意します。足指のマメが気になる人は5本指で摩擦を分散、爪トラブルが多い人はつま先補強のあるモデルが安心。雨予報なら“濡れても冷たく感じにくい”素材を優先しましょう。
- 薄手:軽快・感覚が鋭い/冷えやすい人は注意
- 中厚:汎用性が高く11月の本命
- 丈:シューズ履き口+1〜2cmで擦れ防止
シューズの通気と保温のバランス
アッパーの通気が高いほど汗は抜けますが、風や雨で足先が冷えることがあります。11月は「通気高め+ソックスで微調整」が基本。つま先が冷える人は、通気孔が大きすぎないモデルか、風区間だけつま先に風が当たりにくいフォームを意識(集団の後ろ、風上側の足をわずかに内へ)するのも手。雨天は排水性の良いシューズが軽さを保ちます。インソールは吸水性が高いと重くなるため、速乾・撥水処理のあるタイプや替えを検討しても良いでしょう。
フィット・靴紐・インソールの微調整
寒いと末端の血流が落ち、序盤はいつもよりタイトに感じることがあります。試走では「スタート想定の冷えた状態」と「中盤の温まった状態」の両方でシューレースを調整し、甲の圧迫やつま先の遊びを最適化してください。結び目は解けにくいランナー結びやダブルノット、レース中の緩み対策にエラスティックレースを採用するのも有効です。インソールはクッションよりも「設置感の安定」を重視し、脚のリズムを崩さない選択を。
- フィットは「指先わずかに余裕+甲の圧ゼロ」を狙う
- 雨天は排水性・乾きやすさも評価軸に追加
- 終盤の浮腫みに備え、前足部の締め込み過多を避ける
最後に、シューズの最終決定は「当週の一番走れる日」に短時間のペース走で確認を。11月は日替わりで条件が変わるため、直前の気象とコンディションを反映した“現実の足”の感覚が、紙のスペックより信頼できます。
まとめ
11月は「薄すぎず、重ねて調整」が鉄則。気温帯ごとにベース→ミッド→防風の順で重ね、小物で微調整すれば、汗冷えと冷え込みを両立して抑えられます。スタート前は使い捨て防寒、レース中は脱着容易、ゴール後は即保温を意識しましょう。
- 体感温度は気温±5〜10℃を前提に設計
- 迷ったらアームカバー+薄手シェルで可変性確保
- 擦れ対策と吸汗速乾素材を最優先
自分の走力とコース環境に合わせて「脱ぎやすさ」を基準に選べば、快適性とタイムの両立が可能です。