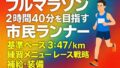- 再開の目安(日数・症状・指標)
- 14日回復プラン(歩く→ジョグ→流し)
- NG行動・セルフケア・補給の要点
フルマラソン後の練習再開はいつから?安全な目安と回復プロセス
ゴール直後の身体は、筋損傷・中枢疲労・自律神経の乱れ・脱水や微量栄養素の枯渇など、表面化しにくいダメージが重なっています。
再開時期の判断で大切なのは「日数だけで決めない」こと。痛みの有無、睡眠の質、安静時心拍、むくみ、食欲など複数のサインを重ねて評価し、段階的に刺激を戻すのが安全です。以下の目安は個人差を前提にした“幅”として使い、違和感が出たら即座に一段階戻す柔軟さを持ちましょう。
完走タイム・経験別の再開目安(幅を持ったガイド)
| タイプ | 再開の目安 | 初期強度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初マラソン完走(サブ5〜6) | 48〜96時間は完全休養→歩行中心→7日目以降ゆるジョグ | 会話可能ペース、20〜30分から | フォーム再学習を最優先 |
| 中級(サブ4前後) | 48時間は極軽いアクティブレスト→4〜7日でジョグ再開 | 心拍ゾーン1〜2、30〜45分 | 流しは2週目に数本のみ |
| 上級(サブ3〜3.5) | 36〜72時間回復優先→4日目以降ジョグ、10〜14日で軽い刺激 | ゾーン1〜2、40〜60分 | 長めのウォークを挟む |
客観指標で“戻し過ぎ”を防ぐチェック軸
- 安静時心拍:平常値+5〜10拍が続く日は負荷を上げない。
- 主観的疲労(RPE):ジョグでRPEが4以上なら時間短縮か休養。
- 痛みスケール:0〜10で3以上の痛みは即休止・アイシング・可動域調整。
- 睡眠の質:入眠困難や中途覚醒の増加=自律神経の過負荷サイン。
- むくみ・体重:翌朝の体重増+むくみは炎症・水分管理の見直し合図。
レース後1週間の基本線
1〜2日は“何もしない勇気”。3〜4日は散歩と可動域づくり、5〜7日は呼吸が乱れない超低強度ジョグを20〜30分。走るほど回復が早まるのではなく、「回復が整うほど走りが戻る」。この順序を崩さないことが、結果的に次のトレーニングを早く積める最短ルートです。
再開前にチェックしたい身体のサインとNG行動

再開可否は「痛みがない」「歩行がスムーズ」「安静時心拍が平常圏」「睡眠が回復」「気分が前向き」に揃ったときが目安です。
逆に、内臓疲労や筋ダメージの名残があるときに刺激を入れると、腱・関節・免疫のどこかが破綻しやすくなります。焦りは最大の敵。以下のサインとNG行動を起点に、踏みとどまる判断軸を持ちましょう。
危険サイン早見表
| サイン | 想定原因 | その日の対処 |
|---|---|---|
| 鋭い局所痛(膝・アキレス・足底) | 腱・靭帯への過負荷、炎症残存 | 走らない。アイス10〜15分×数回、可動域ドリル、痛みゼロ基準で翌日に再評価 |
| 階段昇降での筋断裂感 | 筋線維損傷や筋膜の癒着 | ウォークのみ。フォームローラーは痛み0〜1の圧で |
| 安静時心拍上昇+睡眠の質低下 | 自律神経ストレス、回復不足 | 完全休養・入浴は短め・就寝固定、カフェインを午前中に限定 |
| 濃い尿色・頭痛・倦怠感 | 脱水・電解質不足 | 水+電解質、炭水化物、軽いストレッチのみ |
レース後に避けたいNG行動
- 長風呂・サウナ直行:炎症と脱水を助長。初日〜翌日は短時間のぬるめ入浴に限定。
- 翌日の刺激走:脚が軽く感じても神経系は疲弊。フォーム崩れ→痛み連鎖の典型。
- アルコール過多:睡眠質低下と回復遅延。飲むなら水分・電解質・食事を先に。
- 新しいシューズ・インソールを試す:調整要素を増やすと不具合の切り分けが難しくなる。
復帰前セルフチェックリスト
- 階段をスムーズに降りられる(痛みスケール0〜1)。
- ふくらはぎ・大腿の圧痛がほぼ消失。
- 安静時心拍が平常±3拍以内に戻った。
- 連続7時間以上の睡眠が2日連続で確保できた。
- 軽いジャンプ(5回)で違和感なし。
メモ:チェックのどれか一つでも外れたら、その日はウォーク+モビリティに切替。翌日に“やりたくなる余白”を残すほど回復は加速します。
1〜2週間の回復メニュー:ウォーク・ジョグ・クロストレ
レース後14日間は「エンジンを温め直す期間」。量より質、強度よりリズム。低衝撃の運動で血流を促し、関節可動域を整え、ジョグの“心地よさ”を取り戻します。以下は強度に敏感な人でも安全に進めやすい設計例です(症状が出たら必ず一段階戻してください)。
14日スケジュール例(症状ゼロ前提)
| 日 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 1 | 完全休養・散歩15〜20分 | 高たんぱく+炭水化物、短時間入浴 |
| 2 | 散歩20〜40分+モビリティ10分 | 足首・股関節の可動域を最優先 |
| 3 | ウォーク&ジョグ交互20〜30分 | 1分ジョグ+2分ウォーク×繰り返し |
| 4 | ジョグ20〜30分(会話可) | フォームは「背中から押される感覚」を意識 |
| 5 | クロストレ30〜40分(バイク/エリプティカル/スイム) | 無痛・鼻呼吸中心 |
| 6 | ジョグ30〜40分+流し60〜80m×2〜3 | 流しはフォーム確認程度、全力の60% |
| 7 | 完全休養 or 散歩30分 | 睡眠と食事の質を最適化 |
| 8 | ジョグ35〜45分 | 最後に体幹ドリル5分 |
| 9 | クロストレ40〜50分 | ケイデンス一定・心拍ゾーン2以内 |
| 10 | ジョグ40〜50分+流し×3〜4 | 接地時間を短く、腕振りは小さく速く |
| 11 | 可動域+補強(ヒップヒンジ・カーフレイズ) | 痛みゼロで各10〜12回×2セット |
| 12 | ジョグ45〜55分 | 終盤に“少し速め”2〜3分×2回 |
| 13 | クロストレ30分 or 完全休養 | 翌日に備えて余白を作る |
| 14 | ジョグ50〜60分 | 違和感ゼロなら週明けにビルドアップ準備 |
可動域ドリルと体幹スイッチ
- 足首円運動・ヒップオープナー・肩甲骨リズム(各30秒)。
- デッドバグ・ブリッジ・サイドプランク(各20〜30秒×2)。
- 流しは“伸びやかさ”重視、地面を蹴らず重心移動で進む意識。
怪我予防とセルフケア:アイシング・ストレッチ・マッサージ

再開期は“痛む前に整える”が原則です。ハードな圧や強いストレッチは逆効果になりやすく、微細損傷の回復を遅らせることも。ケアは「頻度×ソフト」を合言葉に、小分けで積み重ねましょう。特にアキレス腱・膝蓋腱・股関節前面は再開初期のトラブル頻出ポイントです。
部位別セルフケアの勘所
| 部位 | NGになりやすいケア | 推奨アプローチ |
|---|---|---|
| アキレス腱 | 強すぎるストレッチ | ふくらはぎの軽圧マッサージ→等尺性カーフレイズ5秒×5 |
| 膝(前面) | 膝蓋骨周りの強揉み | 大腿前面をソフトに流す→股関節伸展の可動域改善 |
| 股関節 | 反動を使った開脚 | モビリティサークル・ヒップヒンジで“動的に”整える |
タイミング別ケアの流れ
- 運動前:関節リズムを出す動的ドリル(30秒×3種)。
- 運動後:アイシング10〜15分(違和感がある部位のみ)→軽ストレッチ。
- 就寝前:フォームローラーで“痛気持ちいい未満”の圧で全身を俯瞰。
睡眠・入浴・交代浴の使い分け
睡眠は最高のリカバリー。就寝時刻を固定し、入浴はぬるめで10分以内、交代浴は「温2分→冷30秒」を2〜3セット。深部体温のメリハリがつくと、夜間の微細修復が進み、翌日の脚のだるさが明確に減ります。
ポイント:セルフケアは“効いた感”ではなく“翌朝の軽さ”で評価。痛みが増える刺激はすべてやめる勇気を。
栄養・水分・生活リズムの整え方
回復は「走る以外の24時間」で決まります。糖質でグリコーゲンを戻し、たんぱく質で修復材料を供給、抗酸化食で炎症を落ち着かせ、鉄・亜鉛・電解質で代謝を回し、一定の生活リズムで自律神経を整える。難しい理論よりも、実行しやすい“型”を淡々と積み重ねることが重要です。
回復を加速する栄養の型
| カテゴリ | 目安 | 食品例 |
|---|---|---|
| 糖質 | 運動後は早めに、日中はこまめに | 米・麺・パン・果物・芋類 |
| たんぱく質 | 毎食手のひら1枚分 | 魚・鶏・卵・大豆製品・乳製品 |
| 抗酸化 | 色の濃い野菜+果物を1日2〜3回 | トマト・葉物・ベリー・柑橘 |
| 鉄・亜鉛 | 週に数回しっかり摂取 | 赤身肉・貝類・レバー・鰯・納豆 |
| 電解質 | 汗量が多い日は意識的に | 味噌汁・梅干し・経口補水・スポドリ |
水分・カフェイン・アルコールの扱い
- 起床後コップ1杯→日中は喉の渇き前に少量ずつ。
- カフェインは午前中に限定し、午後は控えめ。
- アルコールは睡眠の質を下げやすい。飲むなら早い時間に少量、同量の水と電解質を併用。
生活リズムを整える3本柱
- 就寝・起床時刻の固定:週末も±1時間以内。
- 朝の自然光+軽い散歩:体内時計をリセット。
- 夕食は就寝2〜3時間前まで:消化負担を軽くし睡眠の質を守る。
次のレースへ向けた再始動計画:期分けとメニュー例
再始動は「再構築期→基礎期→強化期→仕上げ」の流れで、急いでスピードや距離を戻すのではなく、壊れない体で積める量を増やすことが核になります。再開2週目までは回復最優先。その後に目的別のメニューを小さく追加し、週単位で“効き方”を観察しながら微調整しましょう。
期分けの考え方(例)
- 再構築期(〜4週):フォーム・可動域・有酸素土台。ビルドアップは極軽度。
- 基礎期(5〜10週):ジョグ量を増やし、ウィークリーで閾値系を少量。
- 強化期(11〜16週):ロング走・Mペース走・レペティションを目的別に配置。
- 仕上げ(〜レース2週前):量を落とし、質の維持と回復の最大化。
週の基本フレーム(例)
| 曜日 | 内容 | 狙い |
|---|---|---|
| 火 | ジョグ40〜60分+流し | リズム・接地の質 |
| 木 | テンポ走15〜25分 or 閾値インターバル(短時間) | 巡航力の再構築 |
| 土 | ロングジョグ80〜120分(段階的増量) | スタミナ・脂質代謝 |
| 日 | 完全休養 or クロストレ | 回復の上積み |
負荷の戻し方と判断基準
- 週走行距離は症状ゼロを前提に“少し物足りない”水準から段階的に。
- ビルドアップは「呼吸に余裕が残る範囲」で留め、RPEの急上昇を避ける。
- 翌朝の脚の重さが残る場合は、次のポイント練習をジョグに差し替え。
合言葉:“もっと行ける”で止める。余白が翌週の伸びしろになります。
まとめ
再開は「体のサイン>予定表」。最低1週間は回復を最優先にし、2週目から短く軽い刺激で様子見。痛みや睡眠悪化、安静時心拍の上昇が続く日は迷わず休む。栄養・水分・就寝時刻を固定し、走力ではなく“回復力”を積み上げることが近道。
- 迷ったら翌日に回す(痛みゼロで再開)
- 量より質:フォーム・可動域を整える