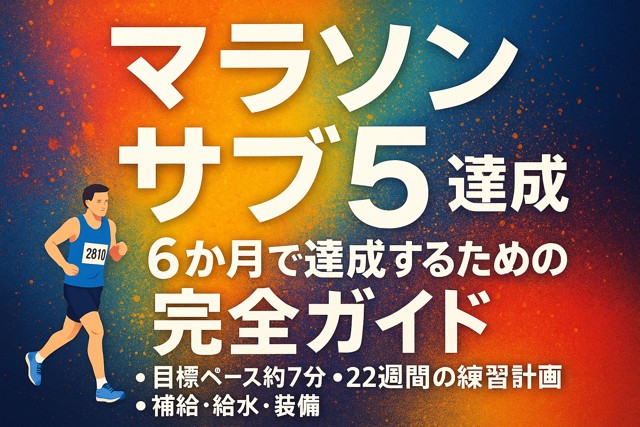マラソン サブ5は、1kmあたり約7分で42.195kmを刻み、関門を確実に越える現実的なゴール。本記事は6か月での達成を前提に、ペース設計、練習計画、装備・補給、当日の動きまでを一本道で解説します。
- 目標ペース:6:55〜7:05/km
- 22週間の週2〜3回メニュー
- ロング走×ペース走の比率
- ジェル・給水のタイミング
- 失速しないレース運び
サブ5の基礎知識と目標ペースの目安
サブ5とは、フルマラソン(42.195km)を5時間未満で完走すること。総時間300分を距離で割ると1kmあたり約7分07秒の巡航が必要になります。渋滞・給水・上り坂・トイレなどのロスを考えると、実走ペースは「6分55秒〜7分05秒/km」に収まるよう余裕を持たせるのが堅実。レースはイベントであり、天候・路面・混雑・メンタルの揺れが当たり前に起こります。だからこそ、事前に“関門(カットオフ)”と“通過目安”を言語化し、当日は時計と体感の両輪で進める設計にしておくと安定して走れます。以下ではサブ5の定義、平均ペース、関門の考え方、通過目安、そして誰が狙いやすいかを整理し、記事全体の土台を作ります。
サブ5の定義と完走条件
公式記録で4時間59分59秒までがサブ5。大会ごとに制限時間や関門地点・閉鎖時刻が異なるため、エントリー前に要確認。制限6時間の大会であっても、サブ5を狙うなら前半の混雑に備えたスタート配置と、コース図での高低確認は必須です。
平均ペースの目安は7:00/km前後
理論値は約7:07/km。現実のロスを織り込むと、平地では6:55〜7:05/km、長い上りは+10〜20秒/km、給水ゾーンでは+10秒/kmを許容し、下りや追い風区間で同程度を回収する「微調整イーブン」を採用します。
各通過地点のタイム目安(5km・10km・ハーフ・30km)
| 距離 | 通過目安(5時間ペース) | 実戦目安(微速) |
|---|---|---|
| 5km | 00:35:33 | 00:35:00〜00:36:30 |
| 10km | 01:11:06 | 01:10:00〜01:12:30 |
| 15km | 01:46:39 | 01:45:00〜01:48:30 |
| 20km | 02:22:12 | 02:20:00〜02:23:30 |
| ハーフ | 02:30:00 | 02:28:00〜02:31:00 |
| 25km | 02:57:45 | 02:55:00〜02:59:30 |
| 30km | 03:33:18 | 03:30:00〜03:35:00 |
| 35km | 04:08:51 | 04:05:00〜04:10:30 |
| 40km | 04:44:24 | 04:40:00〜04:46:00 |
| 42.195km | 05:00:00 | 04:50:00〜04:59:59 |
制限時間・関門とレース選びの注意点
- 制限時間は6時間以上の大会が余裕あり。関門は「橋・狭路・周回切替・交通規制」付近に多い。
- 高低差の少ないコース、スタートブロックが細かい大会は巡航を作りやすい。
- 秋〜冬の気温10〜15℃が発汗・補給管理の面で有利。暑熱はサブ5難度を大幅に上げる。
達成難易度と狙うべき層の目安
10kmを70分、ハーフを2時間30分前後で完走できるなら、6か月の計画でサブ5は十分射程。週2〜3回のラン習慣と、30km走で「7:00/km付近の巡航」を体感できれば当日も崩れにくくなります。
ペース配分の作戦と30kmの壁対策

サブ5の失敗例は「序盤の僅かな貯金」より「中盤の無意識な借金」で起こります。鍵は“微差の管理”。1kmで±5〜10秒の揺らぎを許しつつ、心拍・呼吸・フォームを乱さない帯域に収めます。渋滞・坂・向かい風で焦らず、回収は下りや風裏・直線区間で静かに行う。30kmの壁はエネルギー・筋持久・意思決定疲労の複合現象。補給設計と脚づくり、そして「遅く走る勇気」が対策になります。
イーブンペースの基本と崩さない工夫
- スタート〜5kmは呼吸基準(会話が途切れない程度)で巡航帯に収める。
- オートラップ+手動ラップ併用:混雑区間は区間ラップで体感を補正。
- 信号・鋭角ターン・橋の上り手前は数十mだけ“踏まない”ことで巡航を守る。
ネガティブスプリットの考え方と適用場面
前半は7:05/km、後半を6:55/kmへ微加速する「±10秒設計」。気温が低く風が弱い日、そして後半に下り基調があるコースで有効。前半に余裕が出ても加速は30kmを越えてから。
スタート渋滞・坂・給水ロスの見込みと調整
| 要因 | ロス目安 | 事前策 | 当日回収法 |
|---|---|---|---|
| スタート渋滞 | +30〜90秒/5km | 前方ブロック申請・整列早め | 10〜25kmの下り直線で-5秒/km×6〜10km |
| 上り坂 | +10〜20秒/km | 高低図で力点を把握 | ピーク〜下りでフォームだけ整え自然回復 |
| 給水 | +10秒/回 | 右or左に統一・減速ラインを早め | 給水後200mは接地を柔らかくして再加速 |
30kmの壁を越えるチェックリスト
失速の兆候と即応(タップして展開)
- 脚が重い:腕振りを小刻みに、接地を静かに。1kmだけ+5秒容認。
- 胃がムカつく:次のジェルを見送り、電解質水を小口で3回。
- 集中が散る:100歩カウント法で呼吸と接地を同期。
- 痙攣の気配:歩かずに短歩幅+踵の上下でふくらはぎを緩める。
合言葉:貯金より巡航。1kmの+10秒は、次の2kmで無理せず-5秒×2で整える。
サブ5達成の練習計画(期間別・週構成)
22週間(約6か月)で「基礎→ビルド→特異→テーパー」の4期に分割します。週2〜3回でも伸びるよう、負荷は“面”ではなく“点”で置く。すなわち、ロング走とペース走の柱に、ジョグで回復しながら少量の刺激(流し・坂)を散らす構造。月間走行距離は段階的に増やし、最大期でも無理に200kmへは伸ばさず“質の維持”を優先します。
22週~6か月前の基礎づくりと段階設計
| 期 | 週 | 主目的 | 長い練習 | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎(A) | 1–6 | 有酸素土台・フォーム確立 | 90分ジョグ | RPE4〜5で会話可 |
| ビルド(B) | 7–14 | 巡航感覚・筋持久 | 100–120分ロング+ペース走6–8km | 7:00/km帯で安定 |
| 特異(C) | 15–19 | サブ5速度の耐久 | 25–30km走(補給練習込み) | 30kmでフォーム維持 |
| テーパー | 20–22 | 疲労抜き・体調最適化 | 最長でも16–18km | 睡眠・体重安定 |
週2〜3回で回すメニュー例(平日+週末)
- 週2ラン:平日=ペース走(6–8km)、週末=ロング走(90–150分)。
- 週3ラン:平日①=ジョグ+流し×4、平日②=ペース走、週末=ロング走(隔週でビルドアップ)。
- 補助:週2回の補強(スクワット・カーフレイズ・ヒップヒンジ各10〜15回×2)。
月間走行距離の目安と増やし方の基準
目安は「60→80→100→120→140→最大160km」。同一月内での急増は避け、週あたり前週比+10%以内を原則に。ロング走距離は「最長で30km or 3時間の短い方」を上限とし、2週に1回の長距離に絞ると疲労管理が容易です。
重要な練習(ロング走・ペース走・ビルドアップ)

サブ5の核心は「一定のほどよい速さで、長く、乱れずに走り続ける」こと。よってロング走で脚と補給の耐性を作り、ペース走で巡航帯を身体に刻み、ビルドアップで終盤の微加速耐性を仕上げます。補助としてジョグ+流し、坂道走、フォーム撮影を併用。疲労が溜まるほど“強い練習”の頻度は減らし、1回ごとの質を上げるのがサブ5設計の肝です。
ロング走で脚づくりと補給練習を両立
- 90〜150分、7:10〜7:30/kmで余裕を保つ。特異期は7:00〜7:10/kmに寄せる。
- ジェルは45〜60分ごと、電解質は20〜30分ごとに小口。実戦と同じ銘柄で。
- 後半5kmでフォーム崩れを動画チェック(接地音・左右差・腕振り)。
6:50~7:05/kmのペース走で感覚を養う
6〜10kmから始めて12〜16kmまで拡張。呼吸・接地・腕振り・ピッチ(170〜180目安)を同期させ、ラップの揺れを±5秒に抑える。信号待ち環境では1km周回やトラックを活用。
ジョグ+流し・坂道走で効率よく底上げ
| 練習 | 内容 | 狙い |
|---|---|---|
| ジョグ+流し | 6〜8km+流し80m×4 | 可動域拡大・巡航再現 |
| 坂道走 | 上り60–80m×6(歩いて下る) | 腸腰筋と臀部の活性 |
| ビルドアップ | 5kmごとに-10秒/km×3段 | 終盤耐性・フォーム維持 |
黄金比率:ジョグ6割・ロング2割・ペース走2割。迷ったら「疲れても崩れないフォーム」の練習を選ぶ。
補給・給水・コンディション対策
サブ5は走行時間が長いぶん、エネルギー(炭水化物)・水分・電解質の管理が勝敗を分けます。前日は高糖質+適度な塩分、朝食はスタート3時間前に消化の良い主食中心。当日はスタート30分前にジェル1本+水少量、レース中は45〜60分ごとにジェル、20〜30分ごとに水またはスポドリを小口で。気温や汗量で塩分(ナトリウム)量を調整し、胃腸トラブルを避けるため“種類と摂取リズム”は事前練習で固定します。
エネルギージェルと固形物のタイミング設計
- スタート30分前:ジェル1+水100ml。
- 45–50分ごと:ジェル1(合計4–6本)。甘さに飽きるなら後半に塩味タイプ。
- 30km以降:カフェイン入りで集中を補助(個人差に注意)。
給水間隔・電解質補給と暑熱/寒冷対策
| 気温 | 水分目安(ml/時) | ナトリウム目安(mg/時) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5–10℃ | 300–450 | 200–300 | 喉の渇きが鈍る。定時小口。 |
| 11–20℃ | 400–600 | 300–500 | 最も安定。スポドリ比率↑。 |
| 21–30℃ | 600–900 | 500–700 | 歩かずに飲む工夫。被り水も。 |
当日の朝食とスタート前の整え方
- 主食多め(おにぎり・パン)+少量のたんぱく質。脂質・食物繊維は控えめ。
- トイレ動線を逆算し、整列20–30分前には列へ。
- 寒冷時はレインポンチョ・カイロで待機中の体温を保持。
シューズと装備の選び方
サブ5向けのシューズは「安定したクッション」「素直な反発」「接地の取りやすさ」が条件。厚底レーシングの“跳ね”より、着地〜離地が自然につながる設計を優先します。フィットは踵のホールドと中足部の包まれ感が要。サイズはつま先余り5–10mmを基準に、レース用は練習で最低100kmは馴染ませておきます。ウェアは季節・天候・補給量で構成を変え、携行品は「必要最小限でも“ないことで困らない”」ラインを見極めましょう。
サブ5向けシューズの条件(安定性・反発・クッション)
- スタックハイト30–38mm前後で適度なロッカー。着地音が小さくなるモデルを。
- 足幅は実寸に近いE〜2E程度。甲高は紐で微調整できるもの。
- アウトソールは耐久重視。濡れ路面でのグリップも試走でチェック。
GPSウォッチ・ペーサー・計測アプリの活用
基本は1kmオートラップ+5km手動ラップ。トンネルや高架下での誤差に備え、主役は自分の体感という前提で数値を読むと、崩れにくい。大会の公式ペーサーがいれば、数m後方から“付かず離れず”で風避けと安定を得るのも手。
ウェア・携行品チェックリスト(天候別)
| 条件 | ウェア | 携行品 |
|---|---|---|
| 低温(〜8℃) | 長袖+グローブ+耳当て | ポンチョ・ジェル5–6本・カイロ |
| 中間(9–18℃) | 半袖+アームカバー | ジェル4–5本・電解質タブ |
| 高温(19℃〜) | メッシュ半袖+キャップ | ジェル3–4本・塩タブ・日焼け止め |
| 雨 | 撥水シェル・ツバ広キャップ | 防水ポーチ・予備靴下 |
- 必携:ゼッケン留め・ワセリン(股・足指)・絆創膏(擦れ/爪)。
- あれば便利:薄手の手ぬぐい、軽量ベルト(ジェル固定)。
まとめ
サブ5の核心は「安定した7分前後の巡航」と「計画的な補給」。6か月で土台→30km以降の失速対策→当日運び、の順で整えれば達成率が上がります。
- 週3:ジョグ・ペース走・ロング走
- ジェル60〜75分毎+電解質
- 関門時刻とコース高低を把握
今日から小さく積み上げ、初マラソンを確実にサブ5で。