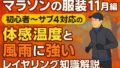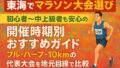- 発汗量の測り方と給水目安
- ナトリウム摂取の考え方
- 吸汗速乾ウェアと冷却小物
- 暑熱順化とペース配分
汗かきは本当に不利か?発汗の役割と勝ち筋
「マラソン 汗かき 不利」という不安は、暑いレースや湿度の高い日本の環境ではよく語られます。しかし汗は体温を捨て、内臓と筋の温度上昇を抑えるための強力な仕組みでもあります。
大量発汗そのものが不利なのではなく、補給・装備・走り方が汗の出方に合っていないときに失速や体調不良として顕在化します。気温・湿度・風の三要素、コース環境(直射・日陰・風抜け)、あなた自身の発汗タイプ(量・塩分濃度)を前提にすれば、汗かきは「熱に強い体」を作りやすい長所にもなり得ます。
このセクションでは、汗のメリットとリスクの両面を整理し、汗かきでも不利にならない設計思想を提示します。
汗が多いと不利になりやすい条件と対策の骨子
| 条件 | 起きやすい不具合 | 骨子対策 |
|---|---|---|
| 高温×無風×高湿 | 蒸散効率低下・体温上昇 | 首・腋・鼠径の冷却、日陰ライン取り、吸汗速乾+通気 |
| 水のみ多量摂取 | 低ナトリウム血症・むくみ | 時間当たりの上限設定、電解質併用、体重差で検証 |
| 綿などの吸水停滞素材 | 汗冷え・擦れ・重さ | 化繊ベース+薄手レイヤー、摩擦部ワセリン |
| 速い入り・過大ペース | 発汗暴発→後半失速 | 入り抑え、風・日陰活用、RPE/心拍管理 |
汗のメリットとリスクを同時に管理する
- メリット:蒸発潜熱で体温を逃がし、暑熱順化が進めば汗はより早く・薄くなり、冷却効率が上がる。
- リスク:脱水、低ナトリウム、汗冷え、擦れ、視界不良(塩結晶・汗滴)、手指ふやけによる補給作業ミス。
- 管理法:発汗量の見える化、給水上限の設定、ナトリウム補給、装備最適化、ペース設計、現場での冷却判断。
タイプ別・汗かきプロファイルと最短解
- 量が多く塩も濃いタイプ
- 電解質低下のリスクが高い。事前に塩タブや高Naドリンクを携行、ジェルはNa表示で選別、キャップ&ヘッドバンドで目に入る汗を遮る。
- 量は多いが塩は薄いタイプ
- 低ナトリウムは「水の飲み過ぎ」で起こりやすい。給水ペースに上限を設け、喉・体感温度・心拍で微調整する。
- 量は普通だが汗冷えしやすいタイプ
- 通気と速乾を優先。濡れた布の停滞を作らないレイヤリングと摩擦部の保護、風区間ではやや抑えめの発汗。
よくある誤解を解くミニQ&A
- Q:汗をかく=スタミナが減る?
A:体温維持のための必要経費。設計次第でむしろ後半が安定する。 - Q:電解質は多いほどよい?
A:「量×時間」で適量を設計。摂り過ぎは胃腸負担や口渇感の錯覚に繋がる。 - Q:水は喉が渇く前に大量に?
A:上限を持たない大量摂取はEAHのリスク。分割・少量・計画的に。
セクション内まとめ
汗かきが不利かどうかは、環境・設計・運用の一致度で決まります。汗を「制御可能な変数」に変え、以降の章で示す順化・補給・装備・走り方・見える化を重ねれば、汗は失速要因からパフォーマンス維持の味方に変わります。
暑熱順化で「汗をかける体」をつくるプロトコル

暑熱順化は、同じ強度でも体温が上がりにくく、汗が早く・薄く出るようになる適応です。汗かきにとっては「たくさん出る汗の質を高める」作業でもあり、レース2〜3週間前から段階的に行うのが基本です。トレーニング内容を変えずに、衣服・時間帯・入浴で熱ストレスを少しずつ与え、内的負荷(心拍・RPE)の反応を観察します。無理な断熱や脱水放置は逆効果なので、必ず安全弁と中止基準をセットにします。
14日スケジュールの例
| 期間 | 刺激の与え方 | ポイント |
|---|---|---|
| Day1–4 | 普段どおり+厚手Tで20–30分の軽走 | 心拍とRPEを観察、終了後に十分補水 |
| Day5–8 | 同様の軽走を40–50分へ、夕方の暖かい時間を選択 | 発汗開始タイミングが早まる変化を確認 |
| Day9–12 | ポイント練のWU/WDを長めに、終盤に温浴10–15分 | 温浴は頭を出して首以下を温める、めまいで即中止 |
| Day13–14 | 刺激量を半分に落とし保守 | 疲労を残さず、体温反応の鈍化を感じ取る |
入浴・サウナ・厚着走の使い分け
- 温浴:短時間・やや熱め、終了後は体温が下がるまで給水してから就寝。
- サウナ:競技週は控えめ。高温×発汗過多は翌日の質を落とす。
- 厚着走:低速・短時間に限定。強度練とセットにしない。
中止基準とセルフチェック
- 寒気、立ちくらみ、悪心、頭痛が出たら即終了。
- 夜間の心拍高止まり(入眠後にも関わらず高い)が続く場合は2–3日中断。
- 体重が継続的に落ちるときは脱水蓄積。補水と塩分を見直す。
順化を維持する日常の工夫
- 炎天下の徒歩や階段を「軽い熱刺激」としてカウント。
- 冷房は睡眠の質を優先しつつ、日中は28–27℃で慣らす。
- 練習日誌に「発汗開始時刻」「汗の質感(べた→さら)」を短文で記録。
セクション内まとめ
暑熱順化は「汗の質」を鍛える最短ルートです。少しの熱刺激を計画的に重ね、異常兆候で即撤退する二段構えにすれば、汗かき体質の強みを安全に引き出せます。
水分と電解質の戦略:脱水と低ナトリウムの両リスク管理
大量発汗のランナーが最も避けたいのは、脱水でペースが維持できなくなることと、水の飲み過ぎで血中ナトリウムが薄まる低ナトリウム血症(EAH)に陥ることです。どちらも「どれだけ汗を失い、どれだけ入れたか」を時間軸で整合させる設計で回避できます。基本は1時間あたり400〜800mlを分割し、気温・体重・発汗タイプで上下させる。ナトリウムは「飲料の濃度」か「タブレット併用」で確保します。
給水・塩分の目安テンプレ
| 気温 | 給水量目安 | Na目安 | 運用例 |
|---|---|---|---|
| 〜15℃ | 300–500ml/時 | 200–300mg/時 | 水+薄めスポドリを交互、ジェルはNa表示を確認 |
| 16–22℃ | 400–700ml/時 | 300–500mg/時 | スポドリ主体+水で口直し、必要に応じ塩タブ |
| 23℃〜 | 600–900ml/時 | 500–700mg/時 | 濃いめドリンク+塩タブ分割、胃の張りに注意 |
症状の見分け方:脱水 vs 低ナトリウム
| 項目 | 脱水傾向 | 低Na傾向 |
|---|---|---|
| 見た目 | 皮膚乾燥、口渇 | 顔のむくみ、指の浮腫 |
| 感覚 | 喉の強い渇き | 水が美味しくなくなる、悪心 |
| パフォーマンス | 心拍高止まり、足攣り | 混乱・ふらつき、けいれん様所見 |
| 対処 | 水+電解質を計画的に追加 | 給水ペースを落としNa補給、医療判断を仰ぐ |
ボトル携行とエイド活用のハイブリッド
- 500mlソフトフラスクを1–2本。片方をスポドリ、片方を水にして使い分け。
- エイドでは「一口で100ml前後」を目安に複数回に分けて飲む。
- ジェルはNa表示(mg)で選び、総量を1時間単位で積み上げる。
失敗パターンを潰すチェックリスト
- 喉の渇きだけで飲む量を決めていないか。
- 「水だけ」で押し切っていないか。
- 給水を大きな間隔でまとめ飲みしていないか。
- Na量を足し算しておらず、勘で済ませていないか。
セクション内まとめ
汗かきが不利にならない鍵は「時間あたりの収支を揃える」こと。給水とナトリウムをテンプレ化し、レース前に自分用へ微調整しておけば、脱水とEAHの挟み撃ちを回避できます。
ウェア・装備で汗を味方にする:素材・小物・保護

「汗が出ること」自体を止めるのではなく、汗が出ても体表で停滞させず、蒸散へつなぐ装備が理想です。同時に、汗で濡れた布が擦れて皮膚トラブルを引き起こすリスクを最小化します。素材は吸って離す化繊ベースを基本に、状況に応じて薄手レイヤーや局所冷却ギアを足します。
ベースレイヤー素材の比較
| 素材 | 特長 | 注意点 | おすすめ用途 |
|---|---|---|---|
| ポリエステル系 | 吸汗速乾・軽量・耐久 | 匂い残りやすい製品あり | 基本のベースとして通年 |
| ナイロン混 | 耐摩耗・肌あたり滑らか | やや乾き遅い製品も | ザック擦れ区間や長距離 |
| メリノウール薄手 | 温度調節・防臭 | 高湿で重くなること | 朝夕の気温差・旅ラン |
| 綿 | 安価・肌触り | 汗を抱えて冷える・重い | レースでは避ける |
頭部・顔まわりの汗対策
- ツバ広キャップで直射と汗滴の目線落下を抑制。
- ヘッドバンドで額の汗を側頭へ逃がし、塩噴きの視界妨害を低減。
- 偏光サングラスで眩しさと飛沫を同時にカット。
擦れ・汗冷えの予防
- ワセリンを乳首・腋・鼠径・かかと・靴下口に薄く塗布。
- シームレスorフラットシームのウェアを選ぶ。
- ソックスは薄手〜中厚で、湿ったら交換できるようレースによっては予備をドロップバッグへ。
収納と給水手段の選び方
| 手段 | 利点 | 留意点 |
|---|---|---|
| ソフトフラスク+ベルト | 揺れ少ない・補給即時 | 腰の擦れ対策が必要 |
| ハンドボトル | 飲む頻度が上がる | 腕振りの左右差に注意 |
| ポケット活用 | 軽装・アクセス性良 | 汗で袋が湿る→個包装対策 |
セクション内まとめ
装備は「汗を蒸発へ導く・摩擦を減らす・補給を簡単にする」の三目的で選びます。汗かきでも装備が合えば不利は解消できます。
ペース配分と走り方:体温を上げすぎない運用術
汗かきの失速は多くが「前半の無自覚な過熱」から始まります。入りを抑え、風・日陰・ミスト・噴水区間を積極的に使い、坂・直射区間では数拍落として体温の暴発を防ぎます。時計のラップだけでなく、RPE(主観的強度)と心拍、体感の熱さ(皮膚温感)を三点クロスチェックするのが実戦的です。
入りの目安と後半ビルドの型
| フル目標ペース | 0–5km | 5–25km | 25–35km | 35km– |
|---|---|---|---|---|
| 5:30/km | 5:35–40 | 5:30±5 | 5:30–35 | 粘りor微ビルド |
| 5:00/km | 5:05–10 | 5:00±5 | 5:00–05 | 微ビルド |
| 4:30/km | 4:35–40 | 4:30±5 | 4:30–35 | 微ビルド |
コース取りと環境の活用
- 日陰側の歩道寄りにラインを取り直射時間を最小化。
- 向かい風区間は集団の後方で風避け、追い風区間は汗の蒸散が落ちるのでペース上げを控える。
- ミストや噴水は首・腋・鼠径に水を当てると冷却効率が高い。
フォーム微調整と熱コストの削減
- ピッチをやや上げ、ストライドを少し詰めると空気抵抗と上下動が減り、発熱も抑えやすい。
- 肩の力みを抜き、手指を軽く開いて血流を保つ。
- 坂はリズム優先。ギア比を落として心拍スパイクを防ぐ。
熱い日の実戦プラン例
| 局面 | 行動 | 目的 |
|---|---|---|
| スタート直後 | 目標より+5〜10秒/km | 発汗暴発の抑制 |
| 日陰区間 | 姿勢を伸ばし呼吸を整える | 体温の沈静化 |
| 直射区間 | 帽子・首元を濡らす | 局所冷却 |
| エイド手前 | 口内を湿らせる予備給水 | 大飲み回避 |
セクション内まとめ
ペースは「体温を乱さないための装置」。汗かきは前半の過熱を抑え、環境を味方に付けるだけで後半の伸びが変わります。
発汗量の見える化と給水設計:体重差テストの使い方
汗かきが不利を跳ね返す決定打は、発汗量の可視化です。体重差テストは自宅でも簡単にでき、あなたの「1時間あたりの発汗量」を具体的な数字で示してくれます。数字がわかれば、給水上限・ナトリウム量・ボトル本数・エイドの寄り方まで全てが設計できます。
体重差テストの手順
- トイレを済ませ、裸または同一の乾いた服で体重を測る。
- 60分走または室内トレッドミルで設定した強度を維持。
- 走行中に飲んだ量をmlで記録、排尿があれば別途記録。
- 終了直後にタオルで軽くぬぐい、同条件で体重を測る。
発汗量の計算式
発汗量(ml/h)= 走前体重 − 走後体重(kg)×1000 + 摂取量(ml) − 排尿量(ml)
例:前後差1.0kg、摂取400ml、排尿0の場合、発汗量は約1400ml/h。給水の上限はこれを超えないようにし、Naは表のテンプレを基準に調整します。
一週間のサマリー表(テンプレ)
| 日付 | 気温/湿度 | 強度 | 発汗量ml/h | 給水ml/h | Na mg/h | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 22℃/60% | E | ||||
| Wed | 26℃/70% | M | ||||
| Sat | 28℃/75% | L |
天候・時間帯別のチューニング要点
- 湿度高:蒸散効率が落ちる→給水上限は据え置き、首・腋の局所冷却を追加。
- 風強:蒸散効率が上がる→給水は変えず、発汗開始が遅れるなら入りを丁寧に。
- 朝夕:直射が弱い→Naは控えめでOKだが、油断せずテンプレ範囲を守る。
リハーサルで本番運用を固定化
- 目標ペースで30–60分のレースペース走を行い、給水とNaの運用を本番通りに。
- ボトル・タブ・ジェルの配置と取り出し動作を時間計測し、最短動線を決める。
- テープやワセリンの量も記録して再現する。
セクション内まとめ
数字がわかれば迷いが消えます。発汗量を起点にした給水・電解質・装備の設計は、汗かきを不利から優位へと反転させます。
まとめ
汗かきでも不利ではありません。体重差で汗量を把握し、1時間400〜800mlを分割給水、ナトリウムを適量補い、吸汗速乾と冷却小物で体温上昇を抑え、暑熱順化と抑えめの入りで後半に粘る。これが失速を防ぐ最短ルートです。